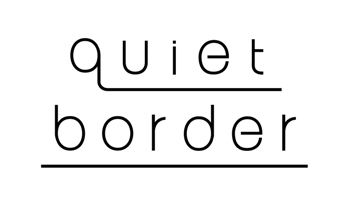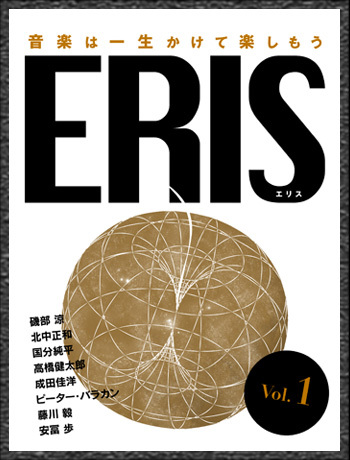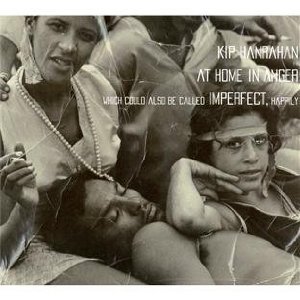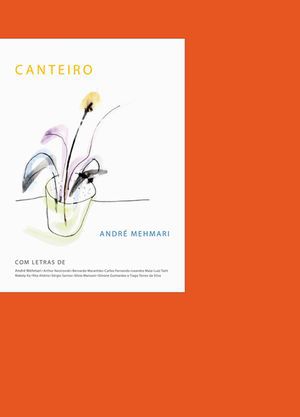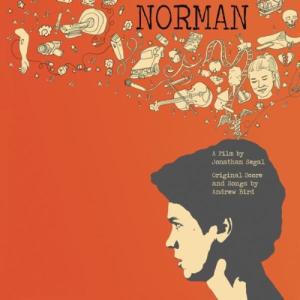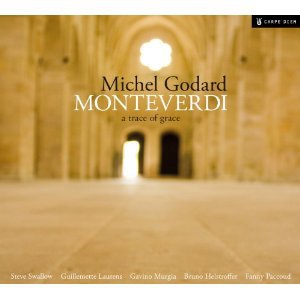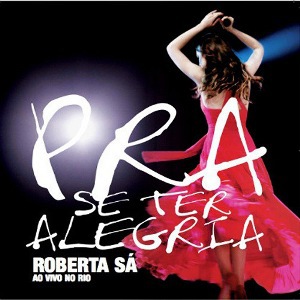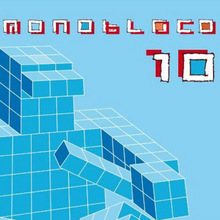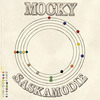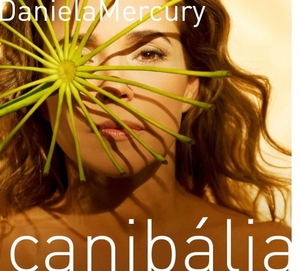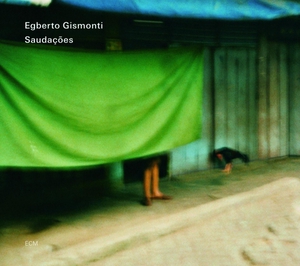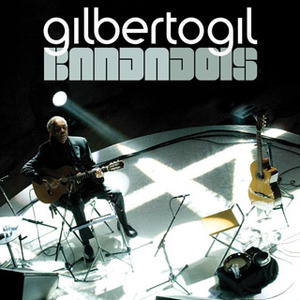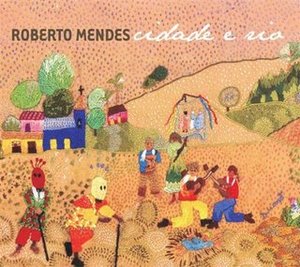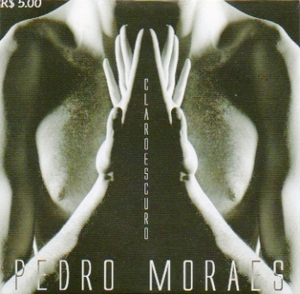2012.11.12
新シリーズ発足のお知らせ
NRTの新しいCDシリーズ<quiet border>が今月よりスタートします。
最初にリリースされる2枚の素晴らしい作品を簡単にご紹介します。
一つ目は、ブラジル・ミナスのシーンから登場した天才マルチ奏者/シンガーソングライター、アントニオ・ロウレイロの2ndアルバム『ソー』。
「ソング」と「インスト音楽」という<ボーダー>を飛び越えた、10年に一度の傑作といえます。
そしてもう一枚は、ギタリスト/コンポーザー、藤本一馬の2ndアルバム『Dialogues』。
カルロス・アギーレ、ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート、北村聡らをゲストに招いた録音で、ジャズや南米音楽といった垣根(ボーダー)の先に広がる美しい作品集となっています。
Antonio Loureiro 『Só』
藤本一馬 『Dialogues』
この後もリリースが続きます。お楽しみに。
2012.10.03
雑誌「ERIS」に寄稿しました
本日ローンチした電子書籍版の音楽雑誌『エリス』誌上にて、連載「クワイエット・ボーダー」を執筆しています。
第一回目のテーマは「南米音楽の静かなる首都、ミナス」。
「エリス」は編集長に高橋健太郎さん、他の執筆陣に磯部涼、北中正和、国分純平、ピーター・バラカン、藤川毅、安冨 歩各氏という豪華さで、しかも無料。
季刊での発行を予定しているようです。
http://eris.jp
ぼくが今回書いたのは、ミナス音楽の内省的な美しさ、独特の浮遊感、複雑なハーモニーはどこから来ているのか、というお話。その音楽を知らない方にも読めるように書きました(そのつもり)。ある種の紀行文のような感じで、気軽に読んでいただければ。
2012.01.24
マリーザ・モンチ 『あなたが本当に知りたいこと』 ディスクレビュー
イントキシケイト誌に寄稿した、マリーザ・モンチ『あなたが本当に知りたいこと』のディスクレビューがTOWER RECORDS ONLINEでもお読みいただけるようになりました。
TOWER RECORDS ONLINE > Marisa Monte 『あなたが本当に知りたいこと』
マリーザ・モンチのサウンドの秘密は、その楽器の組み合わせの妙にある。
2ヶ月ぶりぐらいにこの新作を聴き直してみて、改めてそのように思った次第です。
ライブでもまた体験したいものですね。
2012.01.22
An interview with Kip Hanrahan
現在発売中のラティーナ2月号にて、キップ・ハンラハンに行ったインタビュー記事が掲載されています。
昨年末の来日時に行った取材記事で、5年ぶりの新作『At home in anger』の話題を中心に色んな話を訊くことができた。
以前のエントリーにも書いたけれども、この人の話は脱線の類いが何しろ面白く、泣く泣く削った逸話もたくさんあって……そういう意味では書き手として完全に満足とはいかないものの、それでも一般的なライナーノーツの倍近く、5600字のボリュームで掲載してもらうことができた。
キップが語るシコ・ブアルキ、そして幻に終わったアストル・ピアソラとシコのレコーディングについての逸話もあり、彼の音楽に特別の興味がない方もお目通しいただければ。キップ本人名義の全作品ガイドも紹介しています。他ページではカルロス・ヌニェス&ジョゼ・ミゲルヴィズニッキの快(怪)作『Sem mim』のディスクレビューも執筆しています。
2012.01.04
2012年の、静かなる。
ここ2年ぐらいになるだろうか。クワイエット、とか、静かなる、というキーワードで語られはじめた一群の音楽がある。
誰がそう呼び始めたかわからない。
メディアで華々しく取り上げられているというわけでもない。
その形容詞からストレートに連想されるのは、クラシックの室内楽だろうか。音楽的にはどこかでつながっているように思えるけれど、そのものずばり、ではないらしい。
なのになぜかそのひとことで、どのような音楽のことをさしているかわかる。
ざっと数百~数千人ぐらいのサークルのなかで、現在それは共有されている。
ぼくの周囲で代表的なものとして話題にのぼるアーティストは、こんな感じだ。
アルゼンチンのピアニスト/シンガー・ソングライター、カルロス・アギーレ。ギタリストのキケ・シネシ。
ブラジルのシンガーソングライター・デュオ、ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート。ピアニストのアンドレ・メマーリ。
日本のピアニスト、中島ノブユキ。ギタリストの藤本一馬。
国もカテゴリーもばらばらだけれど、それまでになかったある空気、ムードをまとった音楽家たち。
個人的には北米のミュージシャンたち、たとえばジョアンナ・ニューサムやアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズの音楽もそこに連なるものがあると思う。欧州にもそうした音楽が数多くあるし、人によってさまざまなものがここから足し引きされるに違いない。
◯
ところであの去年の3月以降、ぼくもなかなか音楽を聴く気分になれずにいた。
そもそも朝から晩までレコードを流し続ける習慣からはなれて、けっこうな時間が経っていることもあった。音楽は死なない、という合言葉のもと、テレビや街頭のスピーカーから、隣人の携帯電話から、あらゆる時間と場所にまでそれら音楽が押し寄せてくることにも、いいかげん辟易していた。
だからあの事故の後、あの悪しき計画停電によって静まりかえった街のようす、ほかに何も照らすもののない夜空の素朴な美しさに、自分でも意外なほどほっとしたのだ。スピーカーから響いてくる音楽よりもこどもたちの話し声に耳を傾けていたかったし、自分がその時間をどう過ごすべきかに耳を貸したかった。数日後にも関東全域が死の灰につつまれて滅びてしまうかもしれないのだから。
ぼくが「クワイエット」なるひとつの傾向を、はじめて自分のものとして、いちリスナーとして意識するようになったのは、その3月以降だ。もちろんこれまで何年もヘナートとパトリシアのレコードをつくって、紹介しつづけてきたのだし、一昨年前からは藤本一馬のアルバム制作と宣伝に取り組んできたから、もとより自分のなかでの矛盾はない。2010年ごろから、身近なところでその不思議な符合が話題になる機会も多くあった。ただぼくのなかでそれは、単に自分や、自分と近しい一部のひとびとの趣向のひとつ、共通点の一端であり、それ以上の何かであるとまでは受けとめていなかった。けれど去年はそれまで以上に、行く先々、会う人ごとに、それらがひとつの同じ音楽の仲間であり、またそのように紹介されてしかるべきものと考えられていること、またそうした音楽の視点、聴き方が定着してきていることに気づかされた。そして地震以降、さらに放射能汚染のさなかにあって、これらの音楽がひとかたまりのものとして、自分のなかに残った。浮き彫りになったのは、むしろその他多数の、集中して聴くことのできなくなったもののほうで、たとえば何が難しいといって、いまの状況と本質的なつながりのない音のなかに身をひたすということが、なかなかできない。「音楽は死なない」はその最たるものであるように思う(以降はこれを<死なない音楽>と名づけることにしよう。それらはほんとうに次から次へと出続けることをやめず、消費されることじたいを目的化して生み出されているのだ)。
◯
あるいはいっそ、音楽なんて、一度ぜんぶ死に絶えてしまったほうがいいのかもしれない。
そうしてその後に立ち上ってくる、ひとつひとつの顔をもった静かな声が、
<死なない音楽>に掻き消されることなく、それを必要としている誰かの耳に届けばいい。
そのような時代観にありながら、それでもなお寄り添うことのできるものがあるとしたら、それはどんな音楽だろう。
それは少なからず、数十年、あるいは数百年の時を超えたスケールをもつものになるはずだ。
自然のいとなみをテーマとしたものかもしれないし、
あるときは街に刻まれたひとびとの息吹のようなものかもしれない。
いずれにしてもいま生きている時代にありながら、
その背景として横たわる時間の流れを汲み取ることでうまれた、もしくはその俯瞰自体を描いたものではないだろうか。
10万年後の未来に遺恨を残したわれわれにふさわしい音楽があるとすれば、そのような音楽だけなのだから。
クワイエットと聞いて真っ先にうかぶ「静寂」の意味は、音楽そのものというよりむしろ、それを求める聴きての内に宿るものであり、そうした時間感覚への心の動き、だと思う。
2011年はそれらが顕わになった。そして彼ら音楽家どうしの交流がそれまで以上に進行した年でもあった。
2012年には彼らの新譜が数多く予定されている。そのいくつかは、来日公演も実現するかもしれない。
そうした音楽と、音楽家との出会いを今年は何よりも楽しみにしている。
今年もまた、コンサート会場で会いましょう。
――― 補足: 「静かなる音楽」、その紹介例 ―――
●ライター栗本斉さんのブログ記事 「2010年の終わりに。静かなる音楽」
...旅とリズム...旅の日記 by 栗本斉... > 「2010年の終わりに。静かなる音楽」
ミュージック・マガジン2011年1月号の記事補足。おそらく初めて雑誌媒体に掲載された、「静かなる」についての考察。
●「クワイエット」な音を紹介するフリーペーパー“Quiet Corner”。発行はHMV。web上でも読むことができる。
HMV > Quiet Corner
●上記の編集人、山本勇樹さんも参加する選曲チーム "bar buenos aires"のhp。
bar buenos aires
2011.12.31
【Best Disc 2011】 Kip Hanrahan "At home in anger"
●Kip Hanrahan "At home in anger"
キップ・ハンラハンは、ペシミスティックであることに実はほとほと嫌気がさしているのかもしれない。
アルバム1曲目、歌詞には相変わらずの重さを含みつつ、諦念だけでない気楽さが漂う「Vida sin miel」。キップの長年にわたる盟友でもあるアルフレード・トリフのヴァイオリン演奏を聴いてみてほしい。かつてそこにあった闇、その霧散を思わせる名演である。これまでなら候補からあえて外すような明るい曲調では、との問いに「その通りだが、逆にそれが面白いと思った」などと答えるキップの天邪鬼ぶりは変わらないけれど。
続いてブランドン・ロスのスウィートネスが際立つ2曲目、さらに半ばむりやり編集によってメドレーとしてつなげられたとおぼしき3曲目の、今度はフェルナンド・ソンダースのファルセット・ソウルへの流れなど、まるでマーヴィン・ゲイ『What's going on』のようにメロウな輝きを誇っている。(そういえば、キップの初期の作品にはスモーキー・ロビンソン的なポップスをめざしたというアルバムもあった。今作とは対照的に、あれは彼にとってほとんど唯一の迷走したアルバムではないかと思っているのだが、それはともかく。)
それにしても、オラシオとアミーンのダブル・ドラムスは無敵の奔放さである。ラテン音楽の基本となるクラーベのリズムと四つ打ちとを合体させるこのリズムによって、あらゆる音楽の断片を、同時的に共存させることを可能にした。いまやそこに、楽曲らしさまでが備わりつつある。キップ・ハンラハンはおそろしく多弁な人だが、自分の音楽に対するそのような分析にだけにはのってこようとせず、そういうわけで余談話の比重が多い感はあるものの、それにしてもさんざん面白いを本人から訊くことにもなった。そのインタビューをまとめることから、2012年最初の仕事がスタートする。来年も、よき音楽生活を。よいお年を。
2011.12.31
【Best Disc 2011】 André Mehmari "Canteiro"
●André Mehmari "Canteiro"
※あまりにも圧倒されていて、音楽そのものとはあまり関係ない話かもしれません(世の中にはこういう文章がたくさんあるのでご注意を)。こちらのサンプルを聴きながら、どうぞ。
André Mehmari - CANTEIRO CD 1 (samples) on SoundCloud
André Mehmari - CANTEIRO CD 2 (trechos/samples) on SoundCloud
21世紀ブラジルにおける、最高のピアニスト、最高のアレンジャーということになるのではないか、この人は。
ここ100年にわたるこの国の遺産、名前を挙げるなら――ヴィラ=ロボス、ピシンギーニャ、ハダメス・ニャッタリ、エギベルト・ジスモンチにいたる音楽を継承しつつ、更新する勢いすら感じさせる。その勢いを紐解くべく、耳をこらしてみればみるほどに、すくなくともここ5世紀ぶんほどのクラシック音楽のあれこれが飛びだしてくる。しかもその一瞬ごとに、ブラジル音楽らしい瑞々しさがしっかりと刻まれているのだから。20数種類におよぶ楽器をこなし、素晴らしいコンポーザーでもあり、録音にミックス、マスタリングまでを行なう天才が、自分でもマイクに向かいつつ、10人近くの歌手をゲストに招いて作った「歌もの」アルバム。
完璧すぎるところが唯一の欠点、という表現があるけれど、まさにそんな感じで、綻びのなさがつまらないという意見もわかる。そういう人には、演奏者としての個性がよりわかりやすく出ている他のアルバムをおすすめするべきかもしれない。ピアニストとしても一聴して「この人」とわかる個性、サウンドの持ち主で、そういう面では今年同じくリリースされたバンドリン奏者のアミルトン・ヂ・オランダとのデュオ作『gismontipascoal』を。ただしこちらも、文句の付けどころは微塵もないのだけれど。
2011.12.31
【Best Disc 2011】 Fleet Foxes "Helplessness Blues"
2011.12.31
【Best Disc 2011】 Brad Mehldau, Kevin Hays & Patrick Zimmerli "Modern Music"
●Brad Mehldau, Kevin Hays & Patrick Zimmerli "Modern Music"
ブラッド・メルドーとケヴィン・ヘイズのピアノ・デュオ作品なのだけど、本当にこの二人だけでやってるのだろうか、これって。アーティスト名義としても二人と同等にクレジットされている作曲家、パトリック・ジンマーリの楽曲を中心に、スティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスのカヴァーなども交えたアルバムで、オーネット・コールマンの「ロンリー・ウーマン」などではベースや弦の音すら聞こえてきて、思わずブックレットを端々まで見やってしまった。ジンマーリのことはぼくはよく知らないけれど、ここでの楽曲を聴くかぎりでは、まさにライヒやグラスなどミニマリスト以降の現代音楽作曲家。どの曲もジンマーリがヘッド・アレンジをほどこして、そこに二人の即興演奏が化学反応を加えるという構造らしく、ヘッド・アレンジがあるということは即興パートの指示もあったに違いないのだけれど、実際はそこを大きくはみだして演奏した経緯がライナーにある。右chがメルドー、左chがヘイズで、それぞれのアプローチの個性、二台と曲との関係性は聴き応え充分。ライヒの「Music for 18 musicians」とか、おもしろい。
2011.12.30
【Best Disc 2011】 Dos Orientales "Orienta"
●Dos Orientales "Orienta"
ウルグアイの、というより、南米トップクラスの鍵盤奏者ウーゴ・ファットルーソと、日本のパーカッション奏者ヤヒロトモヒロによるユニットの2作目。ウーゴはミルトン・ナシメントのサポートなどでブラジル音楽ファンにはおなじみだし、矢野顕子のサポートで名前を知った人も多いかもしれない。鍵盤奏者にはめずらしく、グルーヴ重視のプレイヤーで、朴訥とした歌もなかなか味わい深い。そしてなにより彼は最高のコンポーザーでもある。曲想は壮大な大地を思わせるものが多く、リリカルな旋律と野趣が交差する映像性の高いもので、ウルグアイと国境を接するアルゼンチンのパンパやパラナ、そしてブラジル・ミナスの音楽にも相通ずるところがある。それらがときにプログレッシヴな変調、緩急めまぐるしい展開をへて、爽快な疾走感とともに聴き手の前にあらわれる。
ヤヒロのパーカッションはグルーヴ面を支える役割であり、なんとなればソロピアノでも成立する世界かと思っていたのだけど、むしろそのパーカッションこそが楽曲に奥行きを与えているのだということがライブをみてよくわかった。カホンやジャンベ、ツボの低音からシンバルやベル、シェイカーの高音までの空間処理センスとバランスに卓越した個性があって、それらが一音一音の精度の高さ、確かな音程感とあいまって、さながらもう一台のピアノのように美しく、スリリング。いつもあっという間に聴き終わってしまうアルバム。
Ahora Corporation (販売元/試聴)
2011.12.30
【Best Disc 2011】 Laura Veirs "Tumble Bee"
●Laura Veirs "Tumble Bee"
“Sings folk songs for children” と副題にあるとおり、こども向けのアメリカン・フォーク曲を集めたアルバム。ピート・シーガーの2曲にウディ・ガスリー、ハリー・ベラフォンテ「Jump down spin around」などもありつつ、半分は作者不肖のトラディショナル。アメリカン・フォークのこうした企画アルバムは昔からいろいろあるわけだし、まあ、これが特段あたらしい何かってわけでもないかもしれないけど、3月以降なかなか音楽を聴く気分になれなかったりする今、リラックスして楽しめた1枚。口承で伝わってきたこういう曲を譜割りに置こうとすると、えてしてたいへん複雑に、もしくは極度に単調なものになったりするのだけど、あくまで自然に、でもけっこう隅々にまで耳がいくアレンジと演奏に、レベルの高さがうかがえる。
下のメイキングにもあるとおり、自宅のリビングで録音していて、音も柔らく、かつクリア。そんなところもよかったのかな。震災以降しばらく、分厚い防音扉で何重にも囲われたレコーディングスタジオなんて一番怖い場所だったし、その密閉された緊張感の高い空気にこそ、今年はあまり触れる気にならなかったのかもしれない。
2011.12.30
【Best Disc 2011】 Meshell Ndegeocello "Weather"
●Meshell Ndegeocello "Weather"
以下、12/9のツイートより転載。
いつになくアーシー、というかレイドバックしたサウンド。ドラムとベースが安定的にボトムにあって、寡黙なピアノとエレクトリックギターがミニマムに鳴っている。いつもの惑星事故みたいな混沌ではなく、裸足で天体見上げているような。静けさ到来。
posted at 10:41:45, 9 Dec.
クレジットをみると、ベースを弾いているのは彼女ではなく、ほとんどが別の演奏者。あの異物感あふれる蠢きがサウンドの中心に置かれていたから生まれていた混沌だったのだな、これまでは。メンバーはジョー・ヘンリー・バンドの面々だろうか。「J」の棚で確認したい気もするけれど、もう少し待つ。
posted at 10:43:31, 9 Dec.
結局見に行くはめになったではないですか。笑 ピアノのKeefusもですね。いいバンドですね。RT @dubbrock @YoshihiroNarita ギターのクリスは、ジョー・ヘンリー他、ジョン・レジェンドやアラニス・モリセットでも弾いてました。書かないほうが良かったかな 苦笑
posted at 11:03:03, 9 Dec.
2011.12.30
【Best Disc 2011】 Andrew Bird "Norman" (OST)
●Andrew Bird "Norman" (OST)
ヴァイオリンとギターを弾き語りするシンガー・ソングライターとしての活動が有名な人みたいだけれど、これはインスト中心のサントラ作品。もともとチャイコフスキー弾きとして活躍していたようで、そのスコアの静謐で、美しいこと。空間的な作曲センス、曲の中盤でぽろんとピアノが重なり、気配だけを残して消えていくあたりなど、ジョン・ケージのビューティフル・サイドを思わせたりもする。そしてギターを持つと一変、郊外のしなびた光景が広がる。フォークともブルースともつかないギターと歌の世界、こちらはまるでジョン・フェイヒイのアメリカである。同じひとつの国にあって、背景も手触りもまったく異なるそれらの要素が交互に顔を出し、交わりもする、とてもユニークな作り手だと思う。
2011.12.30
【Best Disc 2011】 Monteverdi: A Trace Of Grace / Michel Godard
●Monteverdi: A Trace Of Grace / Michel Godard
セルパン奏者、ミシェル・ゴダールがリーダーのモンテヴェルディ。
歌、セルパン、リュート系の弦楽器テオルボ、そしてヴァイオリンという古くからある楽器に混じって、サックスとエレキベース(しかも奏者はスティーヴ・スワロウ)が入っていたりもするこの編成はかなり珍しいけれど、意欲作ではあっても奇をてらった作品というわけではない。インプロヴァイザーが多くの場合作曲者でもある状況は16世紀~17世紀初期にとても似ている、モーダル音楽と和声をつなげる蝶番(ちょうつがい)というべきモンテヴェルディの音楽に、ジャズのインプロヴァイザーと楽曲、クラシックの楽曲を共存させたかった、とはライナーのゴダール談。
モンテヴェルディの楽曲をはさんで演奏されるゴダールの楽曲とセルパン演奏がすばらしい。約半数をしめる彼のオリジナル曲はやたらとアラビックだが、それもこのアルバムのなかで違和感なく収まっている。素朴なうつくしさを湛えるメロディ、のびのびとした演奏だけがここにはあって、歌と伴奏、歌曲とインスト曲、古典とオリジナル曲とが形式ばらずに、同列に存在している。いま現在そのような音楽家をポピュラー・ミュージックの系譜に生み出せるのはブラジルとアルゼンチンぐらいかもしれない、そしてそれらの音楽にぼくが普遍を感じるのは、そこに共通する音楽的背景があるからかもしれない――そんなことをここ最近感じている。(ちなみにここで普遍という言葉を使って悪ければ、100年とか、死ぬまで飽きない、とかに読みかえてもらっても構わない。)
さらに余談を続けると、ヘナート・モタ&パトリシア・ロバートが歌い奏でるクラシック歌曲のアルバム、というアイデアを以前からもっていて……それは彼らの拠点であり故郷でもあるミナスの音楽の、あの素朴なうつくしさが凝縮されたアルバムになりうるのではないか、そして同時にブラジル歌謡の大きな源流を指ししめすものになるのではないかと、そんな案を温めてもいる(彼らもこのアイデアはまんざらでもないようなので、きっといつの日か)。ゴダールのこのアルバムを聞いて、音楽における「素朴さ」も「新しさ」も、<曲>というかたち以上に、<響き>そのものに含まれるのではないかと思ったりもした。とすればここで試みるべきことは、史実や数世紀前のある時代の楽曲にこだわるのではなく、楽器自体のもつ響き、ときにほぼ失われつつある古楽器などもまじえつつ、奏者と奏者の音の組み合わせに注目することだろうか。そうすることで、普遍さえも飲み込む<現在の音楽>が生まれるかもしれない。
Carpe Diem Records (試聴)
2011.12.29
【Best Disc 2011】 Tatiana Parra & Andrés Beeuwsaert "Aqui"
2011.12.20
ブラジル・ディスク大賞10選、そして<3.11と音楽>について
本日、12月20日発売の月刊ラティーナ1月号にて。
ブラジル・ディスク大賞での10選&コメント。
マリーザ・モンチ過去作レビュー。
季刊『アルテス』書評。
ゼー・ミゲル・ヴィズニッキの新作『Indivisível』レビュー。
と、いずれも重量級の対象について寄稿しているので、ぜひご一読いただければと思います。
(マリーザの新作についてはintoxicate誌にも文章を書いたので、そちらもぜひ。)
ちなみに、ブラジル・ディスク大賞でぼくが挙げた順位はこちら。
①Adriana Calcanhotto / O Micróbio Do Samba [Sony]
②Seu Jorge / Músicas Para Churrasco [Universal]
③Hamilton De Holanda & André Mehmari / Gismontipascoal [Estúdio Monteverdi]
④Naná Vasconcelos / Sinfonia & Batuques [Azul Music]
⑤Milton Nascimento / …E A Gente Sonhando [EMI]
⑥Toninho Horta / Harmonia & Vozes [Minas Records]
⑦Aleh / + Samba [Nossa Música]
⑧Chico Buarque / Chico [Rip Curl Recordings]
⑨Marcelo Camelo / Toque Dela [Zé Pereira]
⑩Eduardo Gudin / Eduardo Gudin [THINK! RECORDS]
10月末までにリリースされたもの、という選考基準があり、12月までのものを入れると半数ほどは入れ替わりそうだけど(余裕があれば後日ご紹介します)、それにしても豊作だったと今年もまた思う。
で、その稿のごく短いコメントにも書いたのだけれど(買って、読んでね)、やはりあの3月の、明日にも世界が終わってしまうのではないかと思った余韻のなかに、今もずっと生きている。
たぶん色んな人がそうであったのと同じように、自分がどんな音楽を必要としているのか、そもそも音楽はこういうとき人々の役に立つのか、もし必要とされるのであれば、音楽を介して自分にも何かができるのだろうか……といった問いに直面せざるをえなかった。いままでそうしたことについては無自覚だったし、むしろ自覚的であることこそを、それこそ無自覚に避けてきたのだと思う。
ところで、<3.11と音楽>という特集をもって創刊した季刊『アルテス』は、これらの問いに真正面から取り組んだ価値ある一冊で、関心のあるかたにはぜひ目を通しいただきたい労作だ。ラティーナでその書評をするにあたって、読みはじめたその日から、ぼくにとっては3月以来の大きな余震に見舞われたようであった(そんな物言いは今どき不謹慎なのかもしれないけれど)。こんな感想を抱くのはぼくだけかもしれないのだが、それはなんとも壮絶な読書体験で、原稿を仕上げるまでの2-3週間、ほとんど口もきけないほどだった。この期間は打ち合わせなども少なかったので、ほぼ外出もせず、ひたすらその問いが指し示すものの意味をみつめた。そしてできあがった原稿を送信した。いつものように締め切りがきたからそうしたわけではない。その問いに、初めて解を見出したからである。その内容については、ラティーナの書評と、来年かたちにできる予定の音楽に、その成果を見ていただきたいと思っている。
それにしても、書評とはむずかしい。レコード評やライブ評を書くのであれば、それを作った人物ではなく、その著作物だけを対象にしていられる。いや、ほんらい書評もそれは同じはずなのだが、書評の場合には、評者もまた、同じく批評にさらされる書き手であるとつねに決まっている。例えばあるレコードを「つまらない」と評したときに、「じゃあお前、もっと上手に歌ってみろ」とは、ふつう言われないのとちがって、書評の場合にそれは、より強い論旨を、あるいは別の視点を、評者もまた提示せねばということに突き当たる。もちろんそれをしない文章もありえるし、そんな風に力む必要などそもそもないのだが、それにしてもたんなる要約か紹介文で終えるには、これはあまりにも切実な本であり、テーマなのだ。評者は後攻めである代わりに、300ページにわたって書かれた本にも、場合によっては1000字で意見をしめさなければならない。そのように他者を評することの矛先を自分にも同時に向けていられるものだけが、批評家たりえる。そして読み応えのある評とはそうしたものだと、ぼくはそう思う。まったくタフな職業で、自分がそれに向いているとは露とも思えず、長年これを続けてきた人々を敬うばかりだ。(まあ、実際には、そんな自覚の欠落している人もいて…自分の書く文章の闇に目をつぶり、自己正当化の固まりとなっているような尊大な人をみるにつけ、ほんとうに、文章とはおそろしいと思う。)
ともかく音楽ファンがこの年末にゆっくり読む本として、今年こんなにふさわしいものもないかもしれない。特集以外のページも、面白いし。毎号購読するであろう雑誌(雑誌なのだ、この量で!)が、またひとつ増えてしまった。
2011.10.26
アドリアーナ・カルカニョット、海のリズム
昨日のモレーノ・ヴェローゾの、ゆるく楽しく、ときに意外なほどの熱さも見せるライブの余韻が醒めやらぬなか…今度はアドリアーナ・カルカニョットの東京公演が二日後に迫っている。
いつもお世話になっているラティーナのF編集長から、そのアドリアーナのアーティスト写真が大量に送られてきた。告知に協力せよ、という結構なプレッシャーである。そんなわけで、たまには提灯記事でも。
…というのが半分冗談のようで本気に思えるようなプロジェクト、最高の招聘である。何しろわが社名の「maritmo」というのも、このアドリアーナの名盤タイトルが由来の一つとなっているぐらいで、思い入れはこちらも深い。“mar” と “ritmo”、つまり「海」と「リズム」が合わさった造語のようだが、調べてみると、これはこれで時折使われることもある言葉らしいことがわかった。彼女のアルバムが念頭にあったわけではなく、好きな言葉を並べ替えてはこねくり回しているうちに、まあ、なんと詩的な組み合わせでしょう、という具合にくっついてしまったのだ。
海とリズム、海のリズム。じっさい、アドリアーナの作風には海の気配がしばしば、濃厚に感じられる。彼女を代表する傑作のひとつ『Marê(潮流)』リリース時のインタビューでも、海に関するトリロジー、つまり3部作の2枚目の作品で、海の雰囲気を持つ曲が集まったと語ってくれたことを思い出す。リオに転居して、物理的な海に接するうちに、海に関する文学や詩、歌に感心を持つようになったとも。そんなコメントがごく自然に受け入れられるような、歌とサウンドである。
ところでよくよく考えてみると、海の香りがする音楽、とは一体どういうことだろうか。海の音、これならわかる。波打ち際にマイクを向けて録音し、第三者に聞かせたならば、誰であろうと疑いなく、それが山ではなく海のものだとわかる。聴く人が彼女の歌詞を全く解さないとしても、ギターやベースや打楽器や歌から漏れ伝わってくる世界が、それを感じさせるとは。船が港を離れ、街が少しづつ遠ざかっていく様子を静かに見守っているような、そんなイメージ。決して急に遠ざかるのではなく、徐々に、確実に、何かを置き去りにしていく。様々な感情が去来しながら、孤独なまでに自由でいる。
アドリアーナの最新作であり、今回の来日ツアーの編成をなす『サンバの微生物』にも、その感覚はしっかり刻まれているように思う。インタビューの類いを全く読んでいない(避けている、なんとなく)ので定かなことはわからないけれど、三部作の最終作として位置づけられた作品ではないだろう。タイトルどおり、サンバという音楽の瞬間を顕微鏡で切り取り、ミニマルに再構築したかのごときサウンドで、音響的にも凄みのある作品なのだが、「漕ぎ出す」感覚はここにもある。波の音に分断され、乱反射しながら、陸上から響いてくるサンバ。
思えば会場の「よみうりホール」が入っているあのビルも、海上船にも似たかたちをしているではないか。
ということで、お席にまだ余裕があるようです。ご予約はお早めに!
来日公演詳細はこちら
Blog Latina
『Moreno Veloso Solo in Tokyo』 ※来日記念盤/限定1,000枚
2011.08.31
Eduardo Gudin / エドゥアルド・グヂン
Eduardo Gudin / エドゥアルド・グヂン (THCD159/THINK!) (2,520円/税込)
ライナーノーツという名の駄文を提供しました。
秋の夜長に、一人きりで、もしくは大切な誰かと聴くのに最高のレコード。3曲で歌っているジャニ・モライスの歌声に、聴けばいつでも恋した気分になります。ブラジルの好きなレコード100枚には間違いなく入るはず。
9/7発売、ぜひ買ってください。
disk union
Eduardo Gudin hp ※こちらでフル試聴できます。
2011.08.01
発信者と流通者
普段こちらではなかなか紹介する機会もないけれど、他社の宣伝や営業などの仕事を頼まれる機会が結構あって、そうした場面で出会った人たちからも、時にたくさんのインスピレーションを分けてもらえる。音楽と直接関係あるような、ないような、今回はそんなお話。
かれこれ7年以上請け負ってきた、バウンディ社と弊社間の販売促進における業務委託契約が、さる7月末日で満了となり、昨日をもって一区切りとなった。
バウンディはいわゆるディストリビューター、アグリゲーターと呼ばれる業態をメインとしている会社である。ディストリビューターとは、CDやLPなどの物流を取り扱う業種をいい、全国のCDショップへの販路を提供し、現物の商品をメーカーからお店に納品、その対価として販売手数料などを徴収する。アグリゲーターは平たくいえばその音楽配信版で、iTunes Storeに代表される音楽配信事業者とレーベル間のハブとなり、データの営業や納品、管理を行っている。日本の同業界シェアのトップを占めるのがこのバウンディという会社で、その膨大な取扱タイトルの中から、ワールドミュージックとジャズのマーケティング、および営業というミッションのもと、ざっと800枚以上のタイトルに関わってきた計算になる。
これらのCDがどんな人たちによって世に送りだされ、どのように宣伝されて、どんなお店や地方で売れていくかという一連の流れを間近にすることができて、大変勉強になった。バウンディのスタッフや契約レーベル、お店の方など、関係各位にはお世話になりっぱなしで、この場を借りてお礼を申し上げます。
ところでこのディストリビューターやアグリゲーターという職種、一般の音楽ファンの話題に登場する機会さえほとんどないけれど、洋楽・邦楽問わずインディーズの世界では欠かすことのできない業種である。
どちらもお店とメーカーとの間に立つことで、市場にとってスムーズかつ効率的な流通を確保することがその存在意義だ。特に小さなレーベル会社にとっては、数千店といわれる日本全国のCDショップや、前述のiTSなどと直接契約を結ぶことは現実的に不可能であり、それらのお店にCDやデータを取り扱ってもらうために、これらの会社との契約が不可欠となるのである。NRTとしても、今のところその全タイトルの流通を、バウンディの販売網を通じて実現してきた。
流通会社におけるマーケティング、販売促進とは一体どんな仕事なのか、もう少し説明してみる。
①各レーベルより新譜リリースの説明を受け、②音や企画内容をもとに、同アーティストの前作タイトルの販売実績や、類似タイトルの販売データなどを調査・分析し、③それに伴う目標受注数や各店舗ごとの販売プランなどを策定、④地区ごとの担当セールスに③を伝え、場合によっては自身でも直接営業セールスを行う。
というのがだいたいの流れだ(自分の場合)。
販売データの調査についてはいくつか方法がある。お店のバイヤーや、前作リリース時のレコード会社にこっそり聞いたり、サウンドスキャンのような調査会社と契約して入手すればいいので、パイプさえあれば特に難しいことはない。それに対して、販売経験を通して培ったノウハウについては、担当者ひとりひとりに個性がある。ある人から見れば売れる見込みのほとんどない、伸びしろのない商品に見えるものが、別の人にとっては意外な注目株であったりする。正直に言えば、好みの問題も多分に関係してくる。自分が気に入る音楽であれば、少なくとも地球上に一人はファンが存在することを実感できるし、プレゼンの熱も自然に入る。またその担当者が好きなジャンルであれば、そこにまつわる情報もたくさん持っているから、戦略上有利なデータを提供しやすい。担当者の腕の見せ所としては、作った本人ですら知らない過去の成功例や可能性、新しい宣伝方法などを提示してみせることにつきる。そしてもちろん、その戦略を注文数という現実に落としこむ術を持たなければ、担当者として、会社としての価値を認められない。
だから実際に、レーベルに対して「これは売れます」などと大口をたたいたものが、実際に注文が集まらなかったりすると、目も当てられないことになる。「お宅の言ったとおり予算をかけて宣伝したのにこの注文数では、うちはつぶれる。一体どうしてくれるのか」と、そこまでストレートにクレームを投げてくる人は少ないけれど、伝わってくる気迫は同じ内容を語っている。だいたい、ワールドミュージックやジャズのレーベルというのは、その音楽が好き、という純粋なところから出発して、オーナーの企画を実現するための会社であることが多いので、概して本気度にブレが少ない上に、一枚一枚に社運がかかっていることも珍しくないのだ。
そういうわけで、時に胃が痛む思いもするけれど、発火点でもあるレーベルオーナーの人たちがどのような哲学で音楽を発信し、理想と現実にどんなかたちで折り合いをつけるのか、そこに居合わせた体験は生きた教訓としか言いようがない。聖人君子のように、音楽がもつ力だけを信じて疑わず、全てを天のなりゆきに任せる人。そもそも予算や締切の管理ができないタイプの人。かと思えば、目的のためには多少ダーティーな手段も厭わないという人もやっぱりいて、お金にモノを言わせて雑誌を会社ごと買収しようと目論む豪傑(?)も時折現れたり。何が正しく、またはそうでないか、参考にする、しないという価値判断よりも、とにかくその人が持つ熱量に当てられて、好きになってしまった音楽も少なからずある。一人の人間が成し遂げられることの大きさ。業界やシステムの不備ばかりが目についたそれまでの自分に、もっと広い物の見方を教えてくれたのも、この人たちだ。はっきり言って、経営センス的なことはほとんど参考にならなかったりするのだけれど(苦笑)、とにかく楽しそうに生きている先達の姿を見ているうちに、どうやら自分も道を踏み外してしまったのかもしれない。
まだまだ世の多くの音楽家たちも、愛憎まみえつつ、どうやら彼らのことが嫌いになれないようでもある。同じアーティストを長く紹介しつづけているレーベルをみると、ことさらそんな想いを強くする。
2011.07.19
マイナーな音楽を広めるために
好きな音楽を「マイナーである」と認めることは、なにかやるせない。
自分の趣味がよっぽど特異なものだという自覚のある人ならともかく、出会った何かに心奪われて、周囲の友人にもそれを奨めずにいられない、というか、自分ひとりで楽しむだけではどうにも満足できず、色んな人に吹聴して回ることに使命感を抱いてしまう気持ちは、音楽ファンに限らず身に覚えがあると思う。
最初はきっと、これだけ素晴らしい音楽がこんなにも無名だなんて不思議だなあ、ぐらいの感慨だったのが、知られていないのはおかしい、いや、こんな良質なものが広まらないのはきっと業界に問題があるからだとか、そもそも幼児期からの音楽教育が、なんていう風にエスカレートしていく人をたくさん知っていて、自分もやはりそんな一人だろうと思う。
宣伝する場面、特に音楽専門以外の、一般誌などの編集者にアプローチする場面でよく実感するのだが、時に初対面の(しかも校了前でテンパッたりしている)相手にようやく時間をもらえても、「30秒で話をまとめてください」なんてゾンザイに言われたりすると、急にバケツで水を浴びさせられたような気分になって、マイナーであること、無名性ゆえのハードルの高さを思い知らされる(何しろこちらは世界一の逸材を売り込む勢いなのである)。しかし考えてみれば、付き合う相手は四六時中このような宣伝攻勢に遭っているわけで、もちろん相手を責めるわけにもいかない。結局のところ、自身の影響力のなさを噛み締め、でも現状やれることからスタートするしかない、そんな開き直りの精神が唯一の立ち返るべき場所だったりする。プロジェクトごとに、いつも100回ぐらい自分に言い聞かせる。ローリング・ストーンズだったら、U2だったらこんな処遇はないだろう、なんて理不尽かつ無意味な憤りを覚えたりもしつつ、また振り出しに戻る。そんな彼らだって、最初は無名の新人に過ぎず、誰かの尽力があって今の地位があるのだから。
有名であること、人気があることが必ずしもゴールであるとは全く思わないけれど、そもそも名前も知らないアーティストについての話を、自分の時間を割いてまで積極的に聞こうという人は稀であって、それはメディアの人だろうと、お客さんであろうと同じだ。だから何はともあれ、興味を持ってもらうことが、とりあえずの目標として定められる。そして有名なアーティストというのはやはり、そこに至るまでに尽力した「誰か」の人数がケタ違いであるというのとほぼ同義だ。媒介者もまたある面ではお客さんであり、お客さんもまた媒介者となって新たな顧客を生んでいく。そのスパイラルがきれいな弧を描き、偶然がまたいくつもの偶然を呼び寄せて、アーティストはブレイクする。規模の大小はともあれ、成功したプロジェクトに携わったことのある人なら、そこに運命じみた不思議な流れを感じて、あの時の私の直感、この音楽が広く受け入れられるはずだという確信は正しかったのだ、そんな感慨に浸ったことがあるに違いない。プロデューサーという仕事はいわば、その本来は神の手によるマスタープランを不遜にも自らの手で設計し、実行していくという、ある意味では思い上がった発想を必要とする(そういう人物のほうが概ね向いているように見える)。もちろん現実はそのように単純ではなく、というか、往々にして予想外の出来事にチャンスが眠っていたりするので、事が走りだしてからは、その不慮の出来事、その時点ではチャンスかどうかもわからず、ひょっとすると予算や時間資源を食いつぶすだけのアクシデントかもしれない物事の連続に翻弄されつつ、瞬発力で対応するというのが実際のところだろう。
◯
ここで自分がやってきたことをひとつ例にさせてもらえば、「現在進行形のブラジル音楽を紹介する」ということがひとつの大きな柱であり、2004年のレーベル立ち上げ当初から目指してきたことなのだけれど、ただ良質なリリースさえ続けていれば、自然にそれらがこの日本で広まっていく、なんて風には到底思えなかったから、いきおい、イベントやら何やらを始めることになったのだ。そもそも独立以前、バイヤー時代の5年間で、新譜を売ることの難しさは身に染みていた。ブラジル音楽自体はこの20年来安定的な人気を保っていて、なかには10万枚以上のセールスに至るものもあるのだが、その殆どは70年代のいわゆる名盤に集中している。つまりもうずっと30年以上も、同じカタログの魅力ばかりが取り上げられてきた状況なのだ(逆にいえばだからこそ名盤とされるわけだけれど)。けれども自分には、日々生まれている音楽が、それらに劣っているとは思えなかった。60年代や70年代のブラジル音楽の人気を転覆させるとはいわないまでも、それと並ぶぐらいに、今現在のブラジル音楽の楽しさを広められたなら。元より自社だけでどうにかできる問題とも思えず、志を同じくする他のレーベル、お店、ライター、DJの面々にも声をかけて、レーベル越境型のCDシリーズ(*註)を企画したり、DJイベントを始めたり、ブラジルからアーティストを招聘してみたり、後に一時期ラジオ番組として展開したりということを、「Samba-Nova」という名前の元にやってきた。
イベントは回を重ねるごとにお客さんも増えるようになり、CDリリースも初回オーダーが安定的に集まるようになってきた。そもそも内容自体、心から素晴らしいと思えるものばかりだし、もし誰も日本盤を出さなければ、輸入盤で数十枚~100枚程度で終わってしまうものを1000枚単位でセールスしてたりするわけだから、そういう意味で何がしかのことをやってきた自負はあるのだけれど、本当に自分がその音楽を広める上でどこまで役立っているかというのは、正直よくわからない。2004年から続けてきたイベントをこのところお休みしているのも、自分が当初是非とも必要としていた、ブラジル音楽を紹介し、送り出すための地盤、コミュニティのような存在がある程度形になり、その中に居ることが当たり前のものと感じられるようになってきているからである。居心地はすこぶる良い。いいのだが、もはやこうなってくると、今度は自分の目の前の人々(および、そこに象徴される限定されたリスナー)のための仕事が、年々日々、比重を増してのしかかってくる。それはもちろんそれだけで十分意味のあることだとわかっていながら、やっぱりどこか予定調和で、もっと大きな可能性へと賭けきれない自分の所在について思い当たってしまう。外に意識を開きつつ、顔の見える人々を大事に、そして目の前の採算性も確保しながら何かを続けるということは、本当に難しい。
そんなわけで、現在はイベントとしてのSamba-Novaについてはレギュラー開催を封印し、新たな枠組みを模索中。普段あまりこうした舞台裏的なことはなかなか筆が進まないのだけれど、なぜもっとイベントやらないのですか、とか、お宅で◯×の新譜を出さないのはおかしいですよ、などなど、色々声をかけられることも多いので、この機会に記しておこうと思った次第。7/30のイベントは、それぞれが今一番刺激を感じているブラジル音楽を久々に聴く機会なので、自分でも最高に楽しみにしています。
加えて本当は、ある時事ネタがモヤモヤの契機となって書きはじめたのだけれど(それゆえこのエントリー名になった)、それはやっぱり途中でどうでもよくなりました。(完)
*CDシリーズ「Samba-Nova Collection」のカタログは下記のとおり。
(L→R)
vol.00 Katia B / Só deixo meu coração na mão de quem pode (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.01 Renato Motha & Patricia Lobato / Dois em Pessoa
vol.02 Miltinho / New Malemolência
vol.03 Bid / Bambas & Biritas vol.1 (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.04 Renato Motha & Patricia Lobato / Planos
vol.05 Teresa Cristina e Grupo Semente / O mundo é meu lugar
vol.06 Martnália / Menino do Rio (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.07 Ana Costa / Meu carnaval (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.08 Bebeto Castilho / Amendoeira
vol.09 Affonsinho / Belê
vol.10 Gabriel Moura / Brasis (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.11 Mariana Baltar / Uma dama também quer se divertir (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.12 Paula Lima / Sinceramente
vol.13 Katia B / Espacial (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.14 Rodrigo Maranhão / Bordado (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
vol.15 Roberta Sá / Que belo estranho dia pra se ter alegria
vol.16 V.A. / Samba-Nova
vol.17 Ana Costa / Novos Alvos (Inpartmaint/Rip Curl Recirdings)
2011.03.20
Message from Renato Motha & Patricia Lobato
東日本大震災にて亡くなられた方々、ご遺族、被災者の方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
2回の来日で親日家となったヘナート・モタ&パトリシア・ロバートより、震災をうけてのメッセージを預かりましたので、こちらでご紹介します。(抄訳)
***
日本で起こっている危機についてのニュースを見守っています。そしてその全てから計りしれなさを感じています。
私たち二人の心と祈りは日本の友人たち、すべてあなた方と共にあります。
みなさん一人ひとりのことを思い浮かべています。心よりの慈しみと感謝とともに。
日本の方々はとても力強い人々ですから、この災いを乗り越えていかれるに違いありません。
みなさまの全てが神とともにあらんことを。便りを待っています。
temos acompanhado as notícias sobre a gravidade do que esta
acontecendo no Japão, e sentimos imensamente por tudo isso. Por favor
diga aos nossos amigos japoneses que todos estão nossos corações e
também em nossas orações, lembramos de cada um deles com muito carinho
e gratidão.
O povo japonês é muito forte e vai vencer mais este grande desafio.
Fiquem todos com Deus e nos dê notícias.
Um grande abraço para todos,
Renato e Patricia
2011.01.10
Best Disc 2010 【All Genre】 Mariana Baraj "Churita"
ダントツの一位、かもしれない。
●Mariana Baraj /Churita
アルゼンチンの女性シンガーが、初めて全曲を自身の楽曲で構成した傑作アルバム。
チャランゴやパーカッションを演奏し、歌うシンガーで、楽曲はフォルクローレに依拠しているのだが、それまでカヴァー中心でやってきたことが信じがたいほど完成度の高い、優れたソングライティング。伸びのあるボーカルを、より自由に、奔放に表現するべく作られた、自分がよりよく歌うことを目指して作られた楽曲であるようにも聴こえる(そういうの好きだね~)。それまでのアヴァンな、または音響派的なアプローチを通過して、赤や茶を思わせるカラフルな印象、大地を感じさせる力強い歌とサウンドを獲得。深い深い夜の闇を感じさせる曲でのコントラストも、お見事。
○
他にも、
Flying Lotus /Cosmogramma
The Chiftains feat. Ry Cooder /San Patricio
Daniel Bernard Roumain /Etudes 4 Violin & Electronix
Antony & The Johnsons /Swanlights
Seeda /Breathe
これらの作品は強く印象に残った。
再発ものでは、
Esteban Jordan /Ahorita
これにつきる。
今年もたくさんのいいレコード、素晴らしいコンサートに出会えますように。
楽しい一年を!
2011.01.10
Best Disc 2010 【All Genre】 Carlos Aguirre Grupo "Carlos Aguirre Grupo"
順不同/本日の2位。
●Carlos Aguirre Grupo /Carlos Aguirre Grupo
ご存知の方が多いかもしれないけれど、念のため。アルゼンチンのコンテンポラリー・フォルクローレ・シーンを代表する作曲家/シンガー/ピアニスト、カルロス・アギーレの記念すべき1stアルバム。現地での発売は2000年だが、まるで2010年の日本でリリースされるのを待っていたような作品、と言ってみる。
フォルクローレ、と聞いた途端「コンドルは飛んでゆく」が脳内再生された貴方に、真っ先に差し出されるべきアルバムかもしれない。
不思議な揺らぎの感覚があるレコードである。彼の生活拠点に隣接する、パラナ河のせせらぎに影響を受けたサウンドで……常套句のように語られるそんな説明も、あながち間違いでもないように思える。
もし本当にそうであったならどれだけ素敵だろうか、今すぐパラナまで確かめに行きたい、その風景をこの目で確かめに行かない人生なんて、、、聴くたびに、呪文のように、そんな思いが頭をかすめる。
グループを構成している二人のギタリストと、ベースプレイヤーの演奏が素晴らしい。ゆるやかな風、ミナス音楽にも通じる浮遊感、水面にちらちらと反射する光の屈折。そんなイメージを生むサウンドは、この3人の貢献によるところが大きいと思う。秋に実現したソロでの来日公演でも、ギターを手にした時のほうが、この音楽の背景がよく表現されていると感じた。ピアノが本分のアーティストであることは疑いようがなく、ギタリストとしてはつたないところもある演奏だったけれど、それでもなおそのギターは、曲の躍動感をより良く伝えていたのである。
サウンド的には様々な要素が溶け合っていて、クラシック、ECM系のジャズから受けた影響の大きさは本人もたびたび語っている。直接話を伺う機会があり、NRTのCDもいくつかプレゼントしたのだけれど、ヘナート・モタのこともちゃんと知っていたり、ブラジル音楽への造詣も深い。ただ、その楽曲、メロディには、それら外の音楽からの影響を感じる瞬間はほとんどない。では一体それは、何でできているのか。
アルゼンチンに、パラナに旅する理由が、これでまた一つ出来てしまった。
2011.01.09
Best Disc 2010 【All Genre】 Joanna Newsom "Have One On Me"
2010年の印象に残った10枚、残りあと3つ。
●Joanna Newsom /Have One On Me
1982年生まれ、カルフォルニア、ネバダ出身の女性シンガー・ソングライター。
5歳のとき両親にハープを弾きたいと頼み、両親もそのことに賛成したものの、地元のハープ教師が年齢的な理由からそれを認めず、代わりにピアノをはじめたそうである(ハープはその後8才から弾きはじめる)。ヴァルドルフ学校で育ったこととか、面白いプロフィールが色々出てくる、なかなかに稀なキャラクター。
フォーキーな自作曲を、ハープを弾きながら歌う20代の女性シンガーで、ヴァン・ダイク・パークスやジム・オルークといったビッグネームの後押しもある、となれば話題にならないほうが不思議なぐらいだが、加えて彼女の場合は、ケイト・ブッシュを引き合いに出される歌声までを持っているのであった。コケティッシュとエキセントリックの間を行き来するような声質で、英語で歌っているのだが、普段耳にする英語の音楽ともどうも様子が違う。音の出所はすごく近くて、耳元で囁かれているように響くのだけど、数秒遅れでようやく意味が頭に入ってくる感じ。猫にテレパシーで語りかけられたとしたらこんな気分だろうか。
ただし本作では、声色のエキセントリックさはやや後退して、あくまで自曲のストーリーテラーに徹している印象。
サウンドもかなり個性的で、ヴァイオリンやチェロ、ヴィオラにヴィオラ・ダ・ガンバを擁する弦楽アレンジをベースに、フルートやクラリネット、オーボエ、バスーンなどの木管、トランペット、トロンボーンの金管も入る。こう書くとゴージャスなサウンドを想像すると思うけれど、実際には音の隙間を大切にした室内楽的アレンジで、特にホーンはかなりピンポイントな配置がなされている。1曲の終盤までじーっとガマンを重ねて、最後の最後にようやく鳴らされる、という具合なのである。
神話的な時間感覚の流れるレコードなのに、見た目も含めたゴシック風味、そしてバンジョー等によってアメリカーナの風も時折もたらされて、ここ10年ぐらいの時流にも符号したマジカルな一枚。
あっ、一枚といいつつ、三枚組なんですけど……。
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 Rufus Wainwright "All Days Are Nights"
Rufus Wainwright /All Days Are Nights
声とピアノ、でもこっちはいわゆる弾き語りで、"UTAU"のコンセプトとはまた全く別の世界観。
クラシックの声楽歌手がピアニストのみをバックに歌うのと同じことを、ルーファスが一人二役でやっている、といえばわかりやすいか。けれども、歌と楽曲はポップス/ロックの範疇にあって、ピアノがクラシカルに振れているというバランス。これ以上何が要るのかといわんばかりの、歌詞と楽曲による私小説世界に思える。(そればっか。)
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 七尾旅人 "Billion Voices"
残りあと、5枚。
●七尾旅人 /Billion Voices
希代の歌声、魅力的なメロディーメイカー、さらにこれほど自在なヴォイス・パフォーマーもそういないのでは。そんなふうに改めて思わせられた、七尾史上最高にポップで、アイデアに溢れた名作。どの瞬間を切り取っても、ヒリヒリするような、圧倒的な生への衝動に満ちている。
本当はその過剰なアイデアを、少し整理して見せることさえできれば……例えば忌野清志郎のように、多くの人々に愛される存在になる可能性さえ秘めていると思う。まあ、そうならなくたって別に構わないけれど。ギターの表現力がもっと増しさえすれば、日本最強のシンガーソングライターになる日もそう遠くないかもしれない。
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 大貫妙子&坂本龍一 "UTAU"
●大貫妙子&坂本龍一 /UTAU
大貫妙子の歌と、坂本龍一のピアノ、それだけ。ただそれだけで、他の楽器、他の音が入る余地はもうない。全く完璧に無いんである。
曲は、多くは坂本龍一のもので、大貫妙子が詞を元々書いていたり、または新たに乗せたりしているものが大半を占めている。
大貫妙子の歌の存在感。抑揚、強弱、声色の使い分けなど、技巧的で、隙のない解釈。加えて、日本語の発声の美しさ。発声と韻、メロディと言葉の相性など、自ら歌詞を書くメリットを最大限に生かしきっている。ちょっと聴き覚えのないぐらい、美しい発声だと思う。
1曲目、これも坂本楽曲の「美貌の青空」。ギクシャクとした、イビツな、鈍い光を放つピアノ。いわゆる<歌もの>作品のピアノ伴奏で、こんなバランスの演奏が他にあるなら、ぜひ聴いてみたい。ほとんど異常な和声感覚と言えないだろうか。不協和音の置き方がどうとか、そういう次元の話ではなく、イマジネーションそのものに猟奇的なものの気配をすら感じる。それはそれは耽美的な世界だけれど、背徳と紙一重の歌詞とも相まって、それを上回る極度の緊張に中毒を起こしてしまう。
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 Natalia Lafourcade "Hu Hu Hu"
●Natalia Lafourcade /Hu Hu Hu
メキシコの森ガール、なんてキャッチコピーも躍っていたような。2010年には再来日もあった。ビヨーク以降の、広い意味でのオルタナティヴを通過した、ポップな女性シンガー・ソングライターの3作目(オーケストラ盤を除く)。これも色彩感とヴァラエティにあふれた楽しいアルバムで、世代も音楽的背景も全く違うけれど、個人的にはブラジルのマリーザ・モンチとアドリアーナ・カルカニョットの姿を、フリエタ・ヴェネガスと彼女に感じたりもする。
ナタリアはほとんどの作詞作曲を行い、ギターや鍵盤、それにおそらく小型パーカッション類も演奏する。後半の4曲では、管弦オーケストラのアレンジまで手がけたり、とかくマルチな才能の持ち主なんである。
僕が観た2010年4月3日、gm tenでのライブでは、基本的に彼女自身によるギターとヴォーカルのみ、ただしヴォーカルにはマイクを2本使用して、片方のマイクではエフェクト&ループを多用する。ギターもまたサンプラーをリアルタイムに使い倒すスタイル。サポート・ギタリストがわりにこのスタイルを採用するとがっかりさせられることが本当に多いのだが、ナタリアの場合、リアルタイムのギターとそのループ音、ヴォーカルの主従関係が1曲のなかで入れ替わる、このセットならではのパフォーマンスを披露していた。で、そんな風にやりたいことは爆発しているけれど、最終的には曲を聴かせたい衝動が勝っている。そしてその楽曲に、私小説的なイマジネーションを感じるのである。
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 Massive Attack "Heligoland"
●Massive Attack /Heligoland
ほの暗く、官能的な、いずれもショートフィルムのような世界観を持つ楽曲揃い。エモーショナルな瞬間を、いかにスタイリッシュに響かせるか。ここに賭けている人たちなのだろうと思う。
そんなアーティストの、当然のように面白いPVはこちらから。
http://massiveattack.com/
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 Sara Tavares "Xinti"
●Sara Tavares /Xinti
カボ・ヴェルデ音楽の若き才能、サラ・タヴァレス。自作自演の女性シンガー・ソングライターだ。生でライブを見た機会はまだないけれど、そのライブDVDを見るだけでも、彼女がいかに優れたパフォーマーか、誰にでもわかると思う。ポルトガル語圏に属するカボ・ヴェルデの音楽は、近年ブラジル音楽ファンからも注目されているけれど、特に彼女の音楽はアフリカン・フィーリングとブラジルの洗練、ポルトガルのサウダーデ感覚を揺るぎなく兼ね備えていて、この国を代表するセザリア・エヴォラ以上に日本の音楽ファンに愛される可能性を秘めている気がする。
いつもいつも大西洋の強い風が吹きつける、ごつごつとした奇景の島々。去っていくことを前提とした港町の音楽。サラ・タヴァレスの出身はリスボンだけれど、移民2世として育った彼女の音楽に、こうした風景が感じられるというのも考えてみれば不思議だ。
特にカボ・ヴェルデに興味がなくても、アコースティック・サウンドによる女性SSWとして、世界のなかでも突出した才能の持ち主だと思う。
2011.01.08
Best Disc 2010 【All Genre】 中島ノブユキ "メランコリア"
ブラジル以外の、2010年ベストの10枚、順不同。
●中島ノブユキ /メランコリア
たとえば、カルロス・アギーレや、ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート。国もジャンルも楽器編成もバラバラだけれど、これらがある共通の感覚を持った音楽として語られ始めて、じわじわと話題を集めた一年。ある人はそれを<メランコリック>と呼んでみたり、誰が言い始めたのか憶えてないけれど<静かなる音楽>と呼びはじめたり。個人的には、それらが自然発生的に顕在化した年として記憶される一年だった。共通しているのは、単に静かであるというより、静寂と寄り添うように存在する音楽であるということ。
どんなかたちであれ、普段は話題として取り上げられる機会が多いとは言えないそうした音楽のリリースが活発化して、コンサートにも人が多く集まった。そういう意味で、それらの音楽を愛する者のひとりとして、こんなに楽しい一年はなかった。
○
前置きが長くなったけれども、中島ノブユキは、その中心アーティストとされる音楽家のひとりだ。優れたピアニストで、同時に優れた作編曲家による本作をひと言でいうならば、室内楽、というあたりにやはり落ち着くだろうか。マーラーの「アダージェット」、ピシンギーニャの古典的サンバ・カンサォン「カリニョーゾ」、ビックス・バイダーベックの「イン・ア・ミスト」などのカヴァーに加えて、自身のオリジナルが並んだレパートリーによる、十分に抑制がきいた、ひたすら美しい音楽集。ただし室内楽とはいっても、中世のお城やコンサートホールではなく、東京の路上が似合う音楽。都会の喧騒のなかにあって、一瞬の静寂を取り戻すために。
ここからは勝手な想像の世界だけれど、ピアノとバンドネオン、チェロを中心としたこのような編成だけでなく、オーケストラや、もしくは3ピースのロックバンドでもいいのだが、例えばそんなフォーマットのために書かれた音楽があったとしたら……抑制への反動が主題となるような、より過激な音楽を聴けるのではという気がしている。深読みするなら、そんなざわめきの気配もここには漂っているように思う。
2010.12.31
【Brasil Best Disc 2010】 #1: Roberta Sá "Pra Se Ter Alegria"
Roberta Sá "Pra Se Ter Alegria"
09年末リリースだったような気もするけれど。やはりDVDのほうが収録曲数は多いものの、CDでも充分楽しさが伝わるライブ・アルバム。
ポップ・ミュージックとしてのサンバを復権させた歌姫で……なんてカタい話は、すでにあちこちに散々書いてきたのでいいとして。楽曲の美しさ、演奏の楽しさと、一緒に歌ったり踊ったりできるポップスとしての強度を、世界のなかのどの音楽に感じるかといえば、僕の場合は他のどれよりも、やはりサンバに感じる。それも例えば、ホベルタ・サーの音楽に。
本作の内容としては、1st、2ndのレパートリーを、その2作のプロデューサーでもあるホドリード・カンペーロの監督のもと具現化したもの。このライブ盤でしか聴けない何かがあるわけではないけれど、ベスト盤代わりに楽しむには最高の内容になっているはず。
今年夏頃リリースされた、弦楽ショーログループ<トリオ・マデイラ・ブラジル>との共作『Quando o canto é reza』も隙のない力作だったけれど、やや表情が硬いというか、表現されている世界観が幾分真面目すぎたところがあるように思う。ホベルタとトリオ・マデイラとの組み合わせで、本作には未収録曲の"Afefé"は静かな幸福感を湛えた最高のサンバで、僕が監修したコンピレーション『Samba-Nova』にも収録したけれど、ここを超える曲は残念ながらなかったと感じている。
ただし想像では、ライブはCDを超える魅力があるような気がしている。今年実現した、ペドロ・ルイスとの連名での来日公演も素晴らしかったし。
○
というわけで、ここまでがブラジル編でした。皆様よいお年を!
年明けにオールジャンル編をアップ予定です。
2010.12.29
【Brasil Best Disc 2010】 #2: Seu Jorge and Almaz "S.T."
Seu Jorge and Almaz "Seu Jorge and Almaz"
こちらも声の人、セウ・ジョルジ。そのブラック特有のノドの色ツヤ、理想的な苦みを含んだ歌声を最初に聴いてすぐ思いついたのが、他ならぬギル・スコット・ヘロン(2004年のbounce誌にもそんなことを書いた)。セウ・ジョルジはまた優れたソングライターでもあって、サンバのマランドラージェン、ならず者の空気を宿した曲を書くことのできる貴重な存在、期待の星、代わりのきかない現代ブラジル最高のスターだ。
細かないきさつは知らないけれど、米Stones Throw傘下のNow Againからリリースされたこのアルバム、先行シングルがロイ・エアーズ"Everybody Loves The Sunshine"だったり、マイケル・ジャクソン"Rock With You"のカヴァーも入っていたり……本当はもっと彼のオリジナルを聴きたいという本音もある。でもこのアルバム、何しろバンドが最高。ナサォン・ズンビをはじめ、ストリート系の尖った作品に欠かせないプピーロ(ドラムス)とルシオ・マイア(ギター)。さらに「シティ・オブ・ゴッド」など、サウンドトラック制作で最も多忙を極めるアントニオ・ピント(ベース)。ダブ/レゲエやファンク、サンバを消化した、重心の低い、オリジナリティあふれるサウンド。ストレートにロックぽさが表に出ている曲はさほど多くないけれど、全体に手ざわりとしてのロック、ほとんど古今東西のロックンロールのクールな部分だけを抽出したかのような感触もあって、クセになる。2・3年ほど前からまた北米のロックをよく聴くようになったけれど、サウンド面での面白さとしては、このAlmazや、カエターノ・ヴェローゾの<セー・バンド>に敵うものはないぐらいだ。
リリース時、全曲フリーダウンロードできて話題になった作品でもありました。このアルバムをベースにしたショートフィルムなんかもあって、面白い。
Now Again / Seu Jorge and Almaz
2010.12.28
【Brasil Best Disc 2010】 #3: Milton Nascimento "... E a gente sonhando"
Milton Nascimento "... E a gente sonhando"
ミルトン・ナシメントは可哀想だ。などと言ってしまうと、その筋のファンから集中砲火を浴びるに決まっているのだが。アーティストとしての一時代を、その声の魅力で築きあげたが故の苦しみ、とでも言うべきものが確実にあるような気がしてならない。実際、この20年以上、どんな力作を送り出したとしても、全盛期とされる1970年代当時と比べて声の状態がどれだけひどいか、またはマシであるかといったことしか、ほとんど語られていないようにも思える。
"A voz do brasil"、「ブラジルの声」と呼ばれるミルトンの声にまだ何の陰りもなかった70年代当時の作品に感涙し続けてきた人たちの気持ちもわからなくはない(僕だっててもちろんそうだ)。だけど、じゃあ、ミルトンの魅力ってそれだけなの?コンポーザーとしてのミルトン、唯一無二の音楽性と芸術性を高いレベルで具現化してきたプロデューサーとしてのミルトンはどうだろう。そうした、まだほとんど明らかにされていないアーティストとしての底力が、トレードマークの声が枯れてきたぶんだけ、十二分に聴き手に迫ってくるような充実作。
教会音楽とインディオ、またはアフリカ性やミナス特有のフォルクローレ感覚の混合に、はたまたボサノヴァ、ジャズ、ビートルズの影響、etc, etc......よく引き合いに出されるフレーズをここでいくら挙げてみても、その魔力からかえって遠ざかってしまうような計り知れなさ。けれども、その謎に惹かれて旅に出た者には、一瞬掠めとることのできるような親しみもちゃんとある。
ちなみにこの作品、試聴することをオススメしません。代わりにといってはなんですが、彼のオフィシャルhpでも。なかなか楽しいサイトです。
http://www.miltonnascimento.com.br/
2010.12.28
【Brasil Best Disc 2010】 #4: Antonia Adnet "Discreta"
Antonia Adnet "Discreta"
あの底抜けに楽しいホベルタ・サーのライブDVDでも、まるで人形かと疑うほどに直立不動のプレイ・スタイルを貫き、かえって異彩を放っていた7弦ギタリストのデビュー作。マリオ・アヂネーの娘さんらしく、父君も連名でプロデュースを担当しています。
サンバやボサノヴァを下敷きにした、すこぶる感じのよい小品ばかりを集めたMPB作品で、ショーロ風のインスト3曲をのぞいて彼女自身がヴォーカルも務めた歌ものアルバム。ボサノヴァ以降、いい意味でアマチュアっぽさを残しつつ、かつ上質な女性シンガーの作品を多く産みだしてきたブラジル音楽界だけど、近頃はなかなかそうした作品に出会う機会も少なく、今年最もよく聴いたアルバムのひとつになった。
半数ほどでカヴァーも交えつつ、残り半分を占めるオリジナル曲がまた良い。2010年の時代性とか気分とか、そんなものに嫌気がさした久々の晴れ間に、ただただ気分を良くしたい時に、あたま空っぽにしてかけておきたい。絶世の美女にもそろそろ飽きてきた今日(こんにち)、思い出のあの日の君に、時計の針を戻してもう一度だけ……あっすいません、音楽はこちらでお試しください。
2010.12.27
【Brasil Best Disc 2010】 #5: Delia Fischer "Presente"
2010年のベストディスク、まずはブラジル編です。さくさく行きます!
○
Delia Fischer "Presente"
ピアニスト、アレンジャー、コンポーザーのデリア・フィシェル(ポルトガル語読み)。1999年にエグベルト・ジスモンチのレーベルCARMOからもアルバムをリリースしていた、というのは最近知った話だけれど、そのジスモンチやエルメート・パスコアルなどもゲスト参加した、なかなか豪華でヴァリエーション豊かなアルバム。
ピアノだけを聴いていると、まさに(ピアニストとしての)ジスモンチの影響下にある、プログレッシヴかつ耽美的な、独特の小宇宙を感じさせるサウンド。ただしそこから受ける印象は、アマゾンや、広大な大地の深遠さを前人未到のスケールで表現しているジスモンチのそれとは違って、ひとりの女性性が内包している宇宙とでも言えばいいだろうか。
大部分の曲で聴くことのできる彼女のヴォーカルの、少し素っ気無い感じの歌も、そんな印象を引き出しているような気がする。
美しく、演奏も最上級で、音楽的な冒険もそこかしこにあるけれど……どことなく、さくら色の親しみやすさ。
2010.09.17
ヘナート・モタ プロデュース作品/chie umezawa 『Flor de mim』
ヘナート・モタ関連の話題が続きますが、こちらもビッグ・ニュースのお知らせです。
小野リサ以降、数多く登場した邦人によるブラジル音楽。その頂点として誰もが認める女性シンガー、chie 改め "chie umezawa" による3rdアルバムが、10/7に発売されます。
今回そのプロデュースを務めたのが、他ならぬヘナート・モタ。
セルソ・フォンセカprod.による1stアルバム、アレックス・フォンセカらのprod.による2ndアルバムに続き、こちらも堂々の全編ブラジル録音で、ヘナートの拠点とするミナスで今年1月にレコーディングされたもの。
このアルバムのセールス・ポイントはいくつかあるけれども、特筆すべきは、マリア・ヒタのサウンドの要となるピアニスト(チアゴ・コスタ)&ベーシスト(シルヴィーニョ・マズッカ)が参加していることはその筆頭。ヘナート・モタも、全世界で100万枚以上を売り上げたマリア・ヒタのデビュー作に自作の「Menina da lua」(本作にも収録)を提供して話題を集めていたから、今回のアルバムはいわば、マリア・ヒタのポジションにchie umezawaがそのまま収まったともいえる内容。
chie umezawa、ヘナート・モタ、マリア・ヒタ。
この三者のうち、いずれかにでも興味のあるリスナーにとっては、ほとんど「まったなし」の話題作であることは間違いない。けれどもアルバムはそんなこととは関係なく、1曲目の“carinhoso”から、ごくシンプルに歌と楽曲を響かせる作品として結実している。
ヘナートといえば最近でこそ、マントラの印象を強く持っている方もいると思うけれども、今作のサウンドは、ヘナートの「正統派MPBアーティスト」としての側面がくっきりと出たプロデュース・ワーク。編成的にも、ピアノ・トリオにギターが補佐的に加わった内容で、例えばCDショップのジャズ・コーナーでかかっていても全く違和感のない、間口の広い作品となっています。
さらに『Flor de mim』発売記念コンサートには、チアゴ・コスタ、そしてヘナート・モタの参加も決定しています!10-11月は何かと話題の来日コンサートが多いですが……こちらもぜひ!
chie umezawa 『Flor de mim』
2010.10.7 release
01. Carinhoso (Pixinguinha)
02. Lugar Comum (João Donato/Gilberto Gil)
03. O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
04. Acontece (Cartola)
05. Beatriz (Chico Buarque/Edú Lobo)
06. Amor de Indio (Ronaldo Bastos/Beto Guedes)
07. Vou Onde o Vento Me Leva (Renato Motha/Patricia Lobato)
08. Flor de Mim (Renato Motha)
09. Menina da Lua (Renato Motha)
10. Farolito (Agustín Lara)
chie umezawa 『Flor de mim』CD&コンサートの詳細はこちら
Rip Curl Recordings
2010.07.21
輸入盤 vs 日本盤

(『カルロス・アギーレ・グルーポ』ジャケット写真。一枚一枚が手書きのイラストで、絵柄も違う、というオリジナル版のコンセプトが日本版でも再現されている。)
半年ほど前からtwitterを始めてみて良かったことの一つに、誰か第三者の思いもよらない意見に出会える、ということがある。
とりわけ僕の場合は、音楽と消費にまつわる話題となると、これはもう、どうしても敏感に反応してしまう。一般の方とプロとを問わず、いやむしろ、普段なかなか話を聞けないユーザーの意見、その一端が垣間見れるのは勉強になるし、色々身につまされたりもする。
自分はリアルタイムで参加できなかったけれど、つい昨日、洋楽ファンの間で輸入版と日本版のどちらを選ぶか、そんな話題が盛り上がっていた。日本版を制作したり発売している立場として、常日頃思うところのある話題で、一般に知られていない事実も多いことがわかったので、以下にまとめてみる。
プロ・アマ問わず、洋楽ファンの購買様式としてあがっていた意見を見ると、大まかにいってこの二つに大別されるみたいだ。
①とにかくオリジナル重視の輸入版派
②解説を読みたいので、できる限り日本版派
だけどそもそも、いわゆる洋楽における輸入版と日本版は、どう違うのか。
端的にいって、発売元が国内か海外か、という定義になるのだが、実際の商品としてはこの三つに大別される。
①輸入版: 海外で制作・製造されたレコードが、既製品として輸入されたもの
②日本版: 海外で制作された音源マスターをもとに、日本でレコードを製造したもの
③輸入版国内仕様: 既製品として輸入された商品に、オビ、解説等を封入し、定価設定して売り出されたもの
この他にも例外は色々あって、盤だけを輸入して、ジャケットは日本で作られたものや、その逆のケースなどもあるけれど、おおまかにいって上記の3種類が存在する。ユーザーとして賢い買い物をするには、まずこのことを知っておくことが肝要だ。
①と②では、ジャケットは別ものと思っていたほうがいい。
そして盤のプレスも、製造している工場が違うので、同じマスターを使用していた場合でも、厳密にいえばその音質には違いがある(もっともこれは、同じ工場の同じライン、同じスタンパーで作られたものであっても、1枚目と5000枚目にプレスされたものでは差異があるわけだけれど)。
とすれば、オリジナルを尊重したい輸入版派としては「それみたことか」となりそうなものだが、実際には日本版のほうが<優れた>商品である場合も少なくない。日本版制作者にとって、輸入版との競合は「宿命」なので、意識的な制作者であればあるほど、輸入版にはないアドバンテージを創出して、ユーザーに選ばれる努力をする。具体的には、日本盤のみのボーナストラックを収録したり、リマスタリングを行ったり、紙ジャケットなどの豪華仕様、歌詞、解説、手に取りやすい価格設定、または世界初CD化など、そもそも日本版でしか入手できない企画の場合もある。
つまるところ、海外版と日本版のどちらが優れているということはなく、オリジナル版を改悪したものも、逆にオリジナルを凌駕する優れた仕事もあるというわけだ。
ところで、いちユーザーとしての自分が商品を選ぶ際には、オリジナル版のリリース元であるレーベルのクオリティと、日本版のライセンシー会社の仕事ぶりをみて、どちらを買うか判断している。
例えば、音の良さに定評があって、アートワークも一貫した美意識を打ち出しているECMやNonesuchといったレーベルの商品なら、迷わずオリジナル版を選ぶことが多い気がする(どうしても解説や歌詞が気になる場合は、日本版を買い足す)。
日本版でも、例えばセレストが発売するタイトルなどは、ジャケットのデザインや、ブックレットに記載されているデータへの信頼があり、なおかつオリジナルの良さを改悪しない確信が個人的にあるので、輸入盤よりも日本版のほうを率先して選ぶことにしている。
そして悲しいことに、ここの日本版だけは絶対買いたくない、というレーベルもいくつか。
NRTでは独自企画による原盤制作も行っているので、全ての例に当てはまるわけではないけれど、ライセンス商品を発売する際は、当然ながら輸入盤よりも総合的に優れた作品として世に送り出せるよう努めています。タイトルによってその長所は違うけれども、いちユーザーとしての視点に立脚しつつ、色んなニーズを盛り込み、出来るかぎり良心的なリリースを心がけています。
当たり前の話だけど、海外の原盤元やアーティストと相談の上、製造を行っているので、オリジナル版を超える商品を作ることは相手先の信用にもつながる。またユーザーにそのことが評価されれば、結果的にいいセールスを生み、ますます海外の音楽を紹介できる(発売できる)という循環を生みやすくする。
実績も信用もほとんど全くのゼロからスタートした当レーベルが、ジルベルト・ジルやアントニオ・カルロス・ジョビンといった世界的巨匠の日本版を発売できるようになったのも、こうした積み重ねがあったりするのである。
考えてみれば、どんなにいいジャケットを作ったとしても、ネット上では質感までは伝わらない。だからこれも時代にそぐわない作り方かもしれない(輸入版が10円でも安ければ、何も考えずにそちらをポチッとしてしまう経験は、自分にも覚えがある)。けれどきっと、お客さんの手に届いたときには、何か感じてもらえるのではないか。報われるかどうかわからない、そんな一線を守りつづけられるかどうか、つまるところそれも制作者の意地みたいなものに依っている。だから自分も、そんな気概が感じられるレーベルのものは、ついつい買ってしまったりする。
個人的にはデジタルで買うこともあるので、その良さも知っているつもりだけれど、物づくりのストーリーを大事にする制作者がいる限りは、パッケージ商品を買い続けるに違いない。
リアル店舗とパッケージ制作者が一蓮托生だという一因も、ここにある。
2010.07.07
「ブラジルかぶれのカナ表記」、または知られざる命名プロセスについて
今まで「できるだけ関わらないように」気をつけてきた、ブラジル・ポルトガル語のカナ表記について、一言。
つまらなそうな話と思った方は、どんどん読みとばしてくださいね。
事の発端は、萩原和也さんのブログの記事「ブラジルかぶれのカナ表記」。
詳しくはそちらの記事を読んでいただきたいけれど、このブラジル・ポルトガル語の問題については、かねてから日本のブラジル音楽ファン、関係者周辺でよく話題に上ってきた。
例えば、Maria Rita。日本人には「マリア・リタ」ではなく、「ヒタ」が発音上・聴感上近い表記として一般化していると思うが、それへの苦言といった内容が、本記事で展開されている。
萩原さんの説を要約すると、ブラジル音楽(というよりポルトガル語)ビギナーにとって、この表記だと「スペルの綴りから大きく外れるのでは、カナ表記の持つ大事な特性を奪うことになるんじゃないでしょうか」と書かれている。引用を続けると、「外来語をカタカナに置き換えること事態が無理なのに、正確さにこだわればこだわるほど、もとの発音を知らない人にはますます伝わらなくなる」との主張。
主流派の一角を占める「ローマ字特性主義」(いま勝手に名づけただけですが)とでもいえる説で、個人的には必ずしも同意見ではないとしても、別の見方もあるということは納得できるし、それ自体を否定をするつもりにはならない。
そのまま半分ぐらい読み進めると、こんな一文も出てくる。
「(発音原理主義的な)表記が不快なのは、要するに、キザったらしいからなんですよ。」
それまでのロジカルな論理を覆すこのフレーズをみて、結局、個人の趣向に基づく一意見だったことがわかって、しかもそれがツイッター上で多くの賛同を得られているのを見たもんだから、なんだかがっくりきてしまった。
それでも普段の自分であれば素通りを決め込むに違いないのだが、なにせ、弊社でリリースしているRoberta Sá、「ホベルタ・サー」までが俎上にあがっているので、こうして書くつもりになった次第。
萩原さんも認めているとおり、「外来語をカタカナに置き換えること事態が無理」なのだから、カナ表記を厳密に定義すること、しようとすること自体が、ナンセンスだ。これに異論のある人はおそらくいないだろう(うーん?いるかもしれないねえ)。だから基本的には、「R」をラ行に訳すべきか、それともハ行にすべきか、そういう「ほとんどどうでもいいような」微小な差について、それぞれが自説を戦わせているだけにすぎない。音楽ファンは特に「自分が一番わかっている」と言いたい傾向が強いからか、こうでなければならない、との論調が自然と多くなってしまいがちなので、そういう議論自体もまあそんなに嫌な気はしない。(第三者からみれば、ほんと、どうでもいいような問題にしか見えないと思うけれども。)
ただし、弊社のリリースしているアーティスト名についてであれば、これははっきり言わせていただきたい。
「ホベルタ・サー」は、Roberta Sáの抄訳ではない。これは日本におけるアーティスト名、つまり芸名であり、他の表記はありえないのだと。
Roberta Sáだけでなく、例えば、Renato Motha。彼のアーティスト名は、弊社では「ヘナート・モタ」と表記して、CDを発売したり、公演を興行したりしている。
ネット上で「レナート・モタ」とか、「ヘナート・モッタ」という表記を稀に見かけるけれど、NRTでリリースしているアーティストとしての“Renato Motha”作品においては誤記であり、ヘタをすると全く違う商品をさしていると認識されることになりかねないということに、その発言者は留意しているだろうか。少なくとも、あえて故意にそのリスクを犯しているということは認識していただきたい、と切に願うものである。
他のレコード会社がどうしているかはよく知らないけれど、弊社では、それが弊社の原盤を保有しているアーティストか否かに関わらず、可能な限り本人やマネージャーとも会って、アーティスト活動全体を見据えたプランニングをしている。繰り返すけれど、「ヘナート・モタ」は訳ではなく、日本語の「芸名」を「命名」したものなのだ。なので、ここで誰かが、いや、彼の名はレナートさんだ、といった瞬間に、その人は誰か別のアーティストについて語っていることになる。
日本名を命名するときには、自分の感覚だけでなく、考えつくあらゆる意見を並べて、そのメリット・デメリットを推し量る。可能であれば、本人にも日本語風の読みを伝えて、これでいきますよという話をする。当然カタカナについての語感がない人が相手なので、厳密なニュアンスを理解できるわけではないけれど、少なくとも本人が「発音されたくない」表記にしてしまうことは、これで防げる。
そうしたプロセスを経ているという事実を知らない人が多いと思うので、思いきって書いてみました(それにもちろん、一方的にキザと言われっぱなしなのも嬉しくないし)。
でも、とにかく書いてみて良かったことが一つ。
今後は同様の論争に巻き込まれそうになったときにも、「ブログの記事を読んでくださいね」という逃げ口上が、これでどうやらできたというわけで…。
2010.06.27
Hermeto Pascoal見聞録/2010.6.27@Pleasure Presure
ポリリズム、変拍子の応酬で、次の展開をまったく予想できない音楽。
にもかかわらず、高尚さとは無縁の、いたってカラフルで、大地や密林の香りがする音楽。
印象としてのエルメート・パスコアルを語れば、ほとんどどのアルバムの、どの曲を聴いても、こんなイメージが浮かんでくる。
エルメート・パスコアル来日公演、2日目(2010年6月27日)1stセット見聞録。
メンバーはエルメートを含め全7人。各ミュージシャンのクレジットはとうとう発表されなかったため不明だが(プロモーターのみなさん、どんなに直前になったとしてもこれだけは発表してほしい)、ベース、ドラムス、パーカッション、エレクトリック・ピアノ、サックス、ヴォーカルの6人に、エルメート自身による様々な楽器が加わる。これを列挙すると、シンセサイザー、ピアニカ、パイプ、フルート、アコーディオン、ヴォーカル、やかん、がこのセットで使用された。他のメンバーも曲によって楽器を持ち替えたり、パートを交換したり、せわしなくステージを出たり入ったりする。1時間強、まったく息もつかせぬめくるめく時間であった。
そもそも、エルメート・パスコアルという音楽家は、一体どのように紹介されているだろうか。
「ブラジルの鬼才マルチ奏者」、「マイルス・デイヴィス・グループに参加した伝説的プレイヤー」、そして、鳥や豚をステージ楽器として使用したり、といったエピソードの数々がすぐに浮かび上がる。僕も数誌の編集者の方たちに本公演を取り上げてもらうため、これらのフレーズを使ってきた。事実その通りだし、高い確立で興味を持ってもらえるのでいいのだけれど、でもその度に何とも言えずもどかしい気分になるのだ。真にオリジナルな音楽を目の前にして、それを職業的に説明せざるを得ない場面で襲われる、あのいつもの無力感。
前回、前々回の来日公演を見ていないので比較はできないけれど、今回のライブを見て、このエルメートにについてまわる「もどかしさ」がいくらか氷解した気がするので、そのことを書いておく。(これまでの来日公演については、中原仁さんのレポートをご参照ください。)
エルメート・パスコアルは、何よりもまず作曲家であり、その<作曲>という行為には、アレンジやサウンドそのものまでを含めたかたちで、リスナーに聴かれるよう意図された音楽なのではないか。そんな印象を持ったコンサートだった。全くの想像だけれど、かなり厳密に記譜された音楽かもしれない、そんなことを思ったショウでもあった。
第一に、彼のグループには、スター・プレイヤーというものがいない。一人ひとりは超絶的なテクニックを持ったミュージシャンだが、曲想がこうも転調やリズム・パターンの変化を繰り返すようでは、ジャズにおけるインプロヴィゼーション、即興演奏の余地はほとんどない。各メンバーは終始、それぞれが主旋律とも副旋律ともつかないフレーズを、まるでちゃぶ台でもひっくりかえすかのようにちらかし続ける。一曲一曲は完全に独立しているが、ほとんど曲間もない。曲の終わりに、次の曲のイントロが鳴らされるように周到にリハーサルされている。何しろ、一つの楽器、一つの楽曲に焦点を絞ることを拒絶するかのような音楽なんである。通常はどんなコンポーザーでも、一曲一曲の陰影が浮き立つような演出を望むのだろうが、その点エルメートは、恐らく、一曲や、5分や10分や30分では足りないに違いないのだ。ショウの間じゅう、リスナーは、あんぐりと口を開けて音の洪水に身を委ねるしかない。つまるところ彼は、そういう「体験」として、観衆に自らの音楽を聴かれることを望んでいるに違いないのではないか。
「フリーキー」という表現で語られることも多いエルメートだけれども、それはあくまで音楽ジャンルとしてのカテゴリー、属性からの自由さであって、演奏形態としてのフリーではないのだなあ、というのがこの日の感想。アンサンブルそのものを聴かせようとする、そのこと自体の強迫観念にも近い執念を感じた。
ではその作曲の源泉がどこにあるかというと、その答えがジャズにないことは自明だが、ブラジル音楽を幅広く聴き込んでいるリスナーであれば、北東部の様々な音楽にそれがあるだろうことは容易に察しがつくだろう。彼が生まれたアラゴアスには行ったことがないので、不勉強にしてよく知らないのだが、フォホーやバイアォンといった彼の地を代表する音楽とも違う、それぞれに独自色をもった音楽が豊富にある。現在74歳のエルメートも、この時代のブラジル人ミュージシャンの例に漏れず、その後ペルナンブーコ~リオ~サンパウロと転居を繰り返すなかで、ルーツとしての北東部性と、ユニヴァーサル・ランゲージとしてのジャズやブラジル南部の音楽を獲得していったのかもしれない。今回のコンサートで最も盛り上がった瞬間のいくつかは、パーカッションがトリアングロ(トライアングル)やパンデイロを叩いている瞬間であり、ベースがスルドの二拍目を強調しているときであり、ヴォーカルのアリーニ・モレーナ(エルメート夫人でもある)がヴィオラ・カイピーラをかき鳴らし、タップのように足音を踏み鳴らした瞬間であったこと、これだけは何をさておき強調しておきたい。
エルメートの音楽はパフォーマンスとしての面白さも充分あるが、レコードにおいてもその魅力が損なわれるものでは決してないので、この来日公演を見逃した向きにも、彼の音楽に向き合ううえで決して遅くないことを記しておきたい。かくいう僕も、彼の全ディスコグラフィ中10枚しか持っていないので偉そうなことは何も言えないのだが、現在比較的手に入り易そうなものとして、『Slaves Mass』『Célebro magnético』『Mundo Verde Esperança』あたりは入門編としてオススメしておきたい。未聴だけれど、折りよく新譜も出たみたいだし。
とかく世界には色んな音楽があるものだなあ、という素朴な感想こそが、日々の活力になるような好奇心旺盛な人たちに聞いて欲しい音楽。
ブラジル音楽ファンにおいては、エグベルト・ジスモンチやウアクチや、はたまたモノブロコのような「規格外」の音楽に耐性のある人が多いので、むしろそれ以外のファンこそ発見の多い音楽ではないか。フェスやレイヴにばっかり通っていそうな当日の客層も、そのことを明示していたようで興味深い。なんだかんだいっても、こんな実験的音楽で1000人あまりが集まる東京・渋谷は、今この瞬間も刺激的な音楽と、人々が交差する場所として機能している。そんなことを感じつつ、鎌倉行きの湘南新宿ラインに乗り込むのであった。
2010.06.09
もうひとつの「音楽の現場」 渋谷篇
※追記(6/10):数店のリンクがうまく貼れておりませんでした。お詫びして訂正いたします。
昨晩このブログで書いたHMV渋谷の閉店に関する記事の反響を色々と頂いていて、メールやtwitter上で寄せられる返信の波がしばらくやみそうにない。
今現在、お店で働いている方の真に迫ったコメントから、CD終焉を象徴するニュースとして捉えようとするものまで実に色んな意見があったけれど、個人的に気になったのは「渋谷に行く理由がなくなった」、そんな意見がちらほらと見受けられたことだった。どんなかたちであれ<現場>というフレーズに触れたコメントが多かったことは、音楽と、音楽を介したコミュニケーションへの渇望感を、みんな持ち続けているのだなあ、という感想を僕にもたらした。
音楽の現場の大きな一角を担ってきたレコード店がこうなってしまうと、この後どんな時代になっていくのだろう……集約すると、そういった不安感が大勢を占めているように思う。
とはいえ、現場はレコード店だけでなく、例えばミュージック・フレンドリーなバーにもあるのでは?
というわけで、何を今更、な名店揃いですが、個人的に足を運ぶことの多いお店を以下に列挙してみます。東京以外に在住の方も参考にしていただければ。
まずは「B+2」としても知られるブラジル系3店:
Bar Blen blen blen
クロい選曲が光ってます。週末のクラブのバーカウンターのような賑わいがあるお店。ご飯もおいしい!
bar bossa
ボサノヴァ好きなら誰もが一度は足を運ぶ名店。林マスターには弊社リリースのジョビンのライナーでもお世話になりました。業界人率も高いワイン・バーです。
barquinho
ヒガシノリュウイチロウさんのお店。実はbar bossa以上にボサノヴァ純度の高いお店。ライブも時々。
Bar Music
今月正式にオープンしたばかり、musicaanossa主催のDJで、元cafe apres-midi店長の中村智昭くんのお店です。午後5時オープンで、コーヒーだけもOKだそうです。
MILLIBAR
基本レゲエ~ニューオリンズなお店です。ここも業界人率高い。スタッフのみなさんも最高!
et sona
元musee~intoxicate編集部の岡崎さんが始めたdining & barです。飲み物はワインが中心、フードもどれもおいしい。ここも隠れ家的で、業界率高いです。予約を入れたほうが無難かも。
NEWPORT
ちょっと代々木八幡方面に足を伸ばせばこんな素敵なお店も。ビオワインでおなじみです。
というわけで、週一度はこれらのお店のどこかで飲んでます。
お店のスタッフもお客さんも面白い人ばかりなので、ぜひ行ってみてくださいね。
2010.06.08
HMV渋谷 閉店のニュースに寄せて
HMV渋谷が今年の8/22をもって閉店する、というニュースは前々から関係者より聞いていたが、今日正式にそのリリースが出たので、思ったことを記しておきたい。
2002年までの約5年間、ぼくはHMVで働いていた。一番長かったのが渋谷店で、このお店にワールドミュージック売り場のスタッフとして入社したのが98年。そんなわけで、閉店のニュースを聞いたその時は、ショックというのか、とにかく二の句がつげない、そんな状態だったことを覚えている。
退社してからもう8年経ったけれども、今でも本社には当時の同僚や先輩がたくさんいるし、渋谷店にも少ないながら、当時からの旧友と呼べる人たちがいる。CDをひたすら触り続ける仕事の合間、ほんのわずかな休憩時間にもレコードの話ばかりしているようなそんな人に限って、CD不況が騒がれようがなんだろうが、今日もショップの店頭に立ち、好きでもない売れ線タイトルの対応に追われながらも、それ以外の地味なタイトルの啓蒙活動に尽力している。
HMV渋谷に限らず、多くの店舗が苦境に立たされている主原因はもちろん、お店の売り上げを支えるヒット作が極端に減ったこと。外資系のメガストアはもちろん、ほとんどのCDショップは、構造的にはいわゆる量販店といえる。その他のカタログ商品をどこまで充実させることができるかについても、結局、ごく一部の売れ筋アイテムの利益が鍵となるのだ。ゆえに、ヒット作が減ったことで、まず最初にニッチなアイテムの在庫が削られて、マニア層の店離れが起こり…という悪循環。
「ワールドミュージックみたいにそもそも限られた数のコミュニティが支えている音楽は、ヒット作の減少がもたらすCD不況の影響はあまり受けないのでは」という質問を業界の内外からよく訊かれるけれど、実情は決してそうではない。これまでお情けで1枚だけ在庫してくれたお店の数がとにかく減ってしまった。レコード会社にとっては、最初の1枚がなければ次の2枚目もないわけで、いまどき在庫がなかったと言って客注してくれるお客さんもいない(だってその場で携帯からポチったほうが数倍早い)。ロングテイルという現象は、これらリアル店舗においては死語と化してしまった。これまで単店で初回100枚注文のあったアイテムが30枚に減ってしまったことはレコード会社・アーティストにとってもちろん痛手だが、最低でも1枚仕入れてくれるお店が100店から30店に減ってしまったことのほうが、長い目でみればより致命的といえるのではないか。ニッチな音楽との出会いのチャンス、その芽とも言うべき現場が、ものすごいスピードで摘まれつつある。
では、リアル店舗はこの先いったいどうすればいいのか。ひとつの答えは、量販店をあきらめて、専門店に回帰することだ。単店で100人を超えるスタッフを擁し、一等地の利便性と、価格競争にこだわるのは止めにして、知識豊富なホンモノのスタッフがいて、買い物以外でもそこに行くと何がしかの出会いが得られるような、そんなお店を目指すのだ。一人ひとりの趣向を嗅ぎ分けて、その時々のオススメを教えてくれる、そういうサービスを求めている人は、自分のまわりにも結構多い。かつてのWAVE六本木店や渋谷クアトロ店のように、中古盤LPのコーナーを併設してもいい。そのための人材は、社内だけでもすでに確保できるのだから。とはいえ、この規模の会社が社員のためのものでなく、株主のものである以上、そんな転換を望むのは難しいのだろうが、マンハッタンにメガストアが一店残らず消えてもOther Musicが生き残っているように、専門店の意義というものはますます貴重なものになっていくのではないだろうか。渋谷という街の求心力、情報発信力の低下が語られて久しいけれど、個人商店が比較的健在な街、例えば首都圏なら谷根千地区や鎌倉といった地域がこの不況下でも人を集めていることを思えば、答えはそこにしかない気がしてならないのである。
お店も会社も無くなったとしても、人材は残る。だからこれまでこの業界を見捨てずにきた人たちには、お店に限らず、色んな場面で活躍し続けていただきたいと思う。レコード店が情報の発信基地となり、そこから色んなシーンが形成されていった時代。少なくともこの2~30年ほどは、レコード店はそんな現場のひとつであったに違いない。<現場感の喪失>ということが言われる音楽シーンにあって、次の現場作りを担う人材の多くは、何より多種多様なお客さんと接してきた、これらのお店にあるはずだと、おこがましくもそう思ってやまないのである。
ありがとう、HMV渋谷。またいつの日か!
2010.04.30
Arthur & Sabrina
東京のブラジル音楽シーンで活動しているデュオ、Arthur & Sabrina。
デビュー作となる彼らのアルバムが、今年6月にランブリング・レコーズよりリリースされます。
正式なプレス・リリースは未確認ですが、この作品のPVも撮影している映像作家のRoberto Maxwellより告知希望とのことなので、一足先にご紹介します。
今までに彼らのライブは色んな形で見ているのだが、実はこの“Arthur & Sabrina”名義のライブを見たことは、まだない。先日お伝えしたDoces Cariocasのウェルカム・パーティーのようなカジュアルな場での演奏を除けば、彼らと数名のメンバーによるバンド“Zamba bem”に、サブリナのソロ名義を体験しているだけだ。しかも、この原稿を書いている時点では、まだアルバムにも耳を通していない始末。にもかかわらずこのエントリーを書く気になったのは、彼らの音楽に、デビュー前の今だからこそ残しておきたい何かを感じているからに他ならない。
Arthur & Sabrinaは、男性ヴォーカル&ギターのアルトゥールと、女性ヴォーカルのサブリナからなるデュオである。
彼らのようにブラジルから日本にやってきて、プロアマ問わず演奏活動をしている人たちは、水面下にいっぱいいる。けれども、その中で比較的良質だとか、本国でも充分に通用するかも、ということぐらいであれば、毎月のようにブラジルのアーティストが来日する今の時代に聴かれるべき理由にはならない筈だ。
では彼らの何が注目に値するのか?ここでは、まだ若干20才のアルトゥールの声と、楽曲の魅力を挙げておきたい。音質が悪くて気が引けるが、まずは一見を。
この“EDO”という曲、歌詞に渋谷や浅草、六本木というフレーズも登場する、アルトゥールのオリジナル曲。アーティスト写真に反して、彼らの音楽は、しごく真っ当なMPB、ブラジリアン・ポップスの系譜を現代に引き継ぐものだが、彼らの音楽がユニークなのは、そうした楽曲とサウンドを通して、今の東京を生きる生活者としての視点が綴られている点だ。
個人的には、個々のアーティストの作品は、その音楽自体によってのみ評価されるべきで、その出自や逸話などのストーリーとは切り離されて語られるべきものだと思っている。その上で、それでも私たちが現在進行形の音楽を、限りなくリアルタイムで享受したいと望む理由はなんだろう。
いささか告白めいた私見を述べれば、いまこの世界に少なくとも誰か一人は、孤独や悲しみと対峙しながら、それでもヒリヒリとした今を存分に生きている。そんな手応えを、音楽を通して知らず知らずのうちに求めているということはないだろうか。アルトゥールの音楽に含まれる孤独に、国籍や出自を超えた接点を感じつつ、同じ都市に暮らしているという幸運を感じるのだ。
と、ここまで書いておいて、全然つまらないアルバムだったら困っちゃいますが。とにかく一度、ライブを体験してもらいたいアーティストです。
アルトゥールの記述に終始してしまいましたが、サブリナについては、また後日。
とりあえず二人のmyspaceでも覗いてください。
2010.04.16
monobloco Japan Tour 2010
文章はとっくに書いていたのだけど、ドーシス・カリオカスのツアーも終了したのでようやく紹介。
結成から10年。リオのカーニバル期、ストリートの風物詩として知られるモノブロコ(モノブロッコ)の初来日が決定。
のっけからミもフタもないことを言ってしまうと、実はこのモノブロコに関しては、これまであまり積極的に追いかけてこなかった。もちろん作品は出るたびに買ってきた(でないと「聴いてないんですか?」と何度も言われるはめになる)。それにもちろん、サンバ・バツカーダ(バトゥカーダ)編成で、サンバ・ヂ・エンヘードからファンキ、ソウル、北東部音楽にニルヴァーナのカヴァーまで、リオのストリートの気分をその時々で表現して支持されてきたそのストーリーには、日本に住むヨソものとしても何かしらの共感を抱いてきた(勝手に)。では、なにがピンとこなかったのか、という点については、必要が生じないかぎりほうっておくようにしているので、ここでは追求しないけれど。
そこへきて、この新作『monobloco 10』、なかなか良いではないですか。
グループの看板だった巨漢シンガー、セルジャォン・ロローザが脱退して、強烈なフロントマンがいなくなったぶん、より市井の雰囲気というか、いい意味でのアマチュアリズムが浸透して、サウンドにも影響を与えている気がする。ヴォーカルを頂点としたアタックの強さ、勢いで一点突破してきたことが通用しなくなり、結果としてレパートリーやアレンジにも、聴衆とのコミュニケーションを通して獲得されたグルーヴが反映されてきた気がするのだ。これまでの出音が「どうだこれがモノブロコだ!Faz barulho! 踊れ踊れ!」というものだったとしたら、今回は「モノブロコっていいますけど、どうぞ遊んでってね。よしじゃ次の曲、こんな感じ!」というように。そもそもが「カーニヴァル・バンド」である彼らを評してこんなことを言うのも妙といえば妙だし、単純に10年の活動でこなれてきたという理由もあるだろうが、表現としての優劣はともかく、ダンス・ミュージックとしては、後者がいつも前者を凌駕する。ダンス・クラシックの名フレーズをリフに取り入れたりするアイデアも、けっこう気がきいている。
そんなわけでこの初来日、とても楽しみにしています。
本当はグループのリーダー、ペドロ・ルイス夫人でもあるホベルタ・サーも一緒に呼べればよかったのだが、またの機会に。
それでは以下に公演情報を。
ワークショップも開催されるとのことなので、詳細はオフィシャル・サイトをclique!
リオデジャネイロの音楽シーンにおいて絶大な人気を誇るストリート・パーカッション軍団、モノブロッコが、結成10周年記念CD/DVD「Monobloco10」(UNIVERSAL MUSIC)を2010年3月にブラジルにてリリースしました。この新作を携えて、遂に初来日!!
ブラジル音楽に造詣の深い宮沢和史(The Boom)をスペシャル・ゲストに迎え、今までに見た事のない超ド級スペシャルライブが、恵比寿リキッドルームにて、遂にその全貌をあらわにします!
東京公演
2010年6月3日(木)&4日(金)
会場:リキッドルーム恵比寿
¥7,000(当日)
¥6,000(前売)
MC: KTa☆brasil
名古屋公演
2010年6月6日(日)
会場:Samba Brazil Japan
入場料(ドリンク別)
¥5,000(当日)
¥4,000(前売)
2010.04.14
Doces Cariocas Japan Tour 2010 / Tour Report (still in progress)
先日このブログでもお伝えしたとおり、それぞれソロ・アルバムを出しているミュージシャン夫婦で、
<ドーシス・カリオカス>名義でも共に作品を発表しているアレクシア・ボンテンポ&ピエール・アデルニが現在来日中。
まずは4/10(土)、カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュでの公演初日。
この日のライブは、ピエール・アデルニがソロで自作曲を披露する前半と、
アレクシア・ボンテンポが登場して、彼女のソロ・アルバム『アストロラビオ』のレパートリーを中心とした後半部との二部構成。
名前の通りフランス系のルーツを持つピエールの音楽には、ボサノヴァ・シンガーの多くが持つクルーナー感ともまた違う繊細さがある。典型的なパリの男性シンガー・ソングライターたち、例えばマチュー・ボガートあたりを思わせる歌い口は、実はありそうでない個性。でももちろんカリオカだけに、パリジャンたちのそれと比べれば、圧倒的にカラっとしている。色気はあるが、気難しさはない。センシティヴだけれど、内気というのではない。「ブラジルのジャック・ジョンソン」というキャッチ・コピーで知られるピエールだけど、たしかに陽性で、潮の香りがするフォーキーな魅力がある。
一方のアレクシア・ボンテンポも、アメリカ系とブラジル人のハーフで、7才までをワシントンDCに暮らし、その後もブラジルとアメリカを行き来する生活を経てきた。まだ20代前半の彼女が登場して歌い始めると、その場がグッと華やかになる。場内に満たされる「いい女」オーラ。ブラジルの、リオの、現代のイパネマに生きる娘の佇まいを、なめらかな美声が加速させる。彼女の歌声は女性的なふくよかさに溢れているけれど、余韻はとてもすっきりとして、ベタつくことがない。彼女が歌うどんな曲も、まるで彼女の私小説のように聴こえるのだが、それでいて聴き飽きることがないのはそのせいだ。ちなみにアレクシアの2ndアルバムとなる次作は、カエターノ・ヴェローゾの英語詞曲を取り上げる内容で、プロデュースにはアドリアーナ・カルカニョットの別名プロジェクト「アドリアーナ・パルチンピン」のプロデューサー、デー・パルメイラが担当することが決まっているというから、ブラジルでもさらに注目のシンガーになることは間違いないだろう。
こちらは日付変わって4/13、渋谷カフェ・アプレミディでのウェルカム・パーティー。
実は今回のツアーでは、日本酒や寿司好き二人の「オフ担当」として、ライブ後の打ち上げ、鎌倉観光&拙宅でのランチ・パーティー、そしてこの東京でのパーティーの幹事を仰せつかったのだが、ショウ本番はもちろん、こうしたパーソナルな場で聴く二人の音楽はまた格別な味わいがある。
ソファに寄り添い、マイクを通さずにつむがれる静かな音楽。集まった人々がそっと耳をそばだてるなか、音楽が生まれた瞬間のよろこびを多くの友人たちと共有できる、濃密で幸せな時間。二人が三曲ほど演奏してくれたこの後も、6月にアルバム発売が決まったサブリナ&アルトゥール、昨年のヘナート・モタ&パトリシア・ロバート来日時のパーティーにも参加してくれた日野良一くんにも歌ってもらったが、この二組の音楽にはピエールも驚きを隠せない様子。最後にヒロチカーノ氏の先導で「サンバ・サラヴァ」をみんなで歌ったり。ボサノヴァ好きなら誰もがタイムスリップして見てみたい、ナラ・レオンのアパートを思わせる光景だね、との声があちこちで上がっていた。ピエールにそのことを伝えると、本当にその通りだ、でも我が家もいつもこんな風だよ。いつでもたくさんの仲間たち、料理とお酒と音楽であふれてる、お前もウチに泊まりに来い、と。ピエールは共作の多いコンポーザーで、ホドリーゴ・マラニャォンやダヂをはじめ、セウ・ジョルジ、ドメニコ、ガブリエル・モウラらと曲を書いているのだけど、いつもこんな場が発端になっているのだろう。20代前半のときに立ち合わせたら、一発で音楽に対する価値観が、もっと言えば人生が大きく変わっただろう、そんなことを思わせる、静かでゆるぎない音楽と、賑やかなパーティーだった。
したたかに酔っ払っていたため記憶があやふやなのだが、この日来ていただいた中原仁さんも「こういう雰囲気をそのまま、一般のファンにも見せられる場があればいい」ということを言われていた。うん、本当にそういう場を作れれば最高だなと、このことは宿題としてまた考えてみることにしよう。
残り2公演、4/17(金)青山EATS and MEETS Cay、そして翌18(土)の山形・山寺 風雅の国 馳走舍(リンク先は公演主催の山形ブラジル音楽普及協会)は、どちらもインティメイトな雰囲気を味わえる素敵な空間です。(山形は桜も?)
間近で楽しめるこのチャンスにぜひ!
ツアー詳細はこちら(CD試聴のリンクもあります)
制作・企画:Rip Curl Recordings / インパートメント
2010.03.16
Alexia Bomtempo & Pierre Aderne ~Doces Cariocas Japan Tour 2010
それぞれソロ・アルバムを出しているミュージシャン夫婦でもあり、
<ドーシス・カリオカス>名義でも作品を発表しているアレクシア・ボンテンポ&ピエール・アデルニの公演が、
4月9日から17日まで、全国4箇所で行われます。
ダヂがプロデュースしたアレクシアのアルバム『アストロラビオ』は、ネオアコMPBの好盤で、爽やかなこの時期のおすすめです。07年のピエール・アデルニ来日公演もよかったので、私もどこかの公演に顔を出すつもり。
詳細はこちらでチェックを。
2010.01.30
“Twitter” はじめました。
2010.01.30
Renato Motha & Patricia Lobato “Mantra Session” with orchestra
ヘナート・モタ&パトリシア・ロバートが09年12月20日に行った、弦楽オーケストラとの共演コンサート動画をUPします。
レパートリーはすべて、インドの「マントラ」にオリジナルのメロディを付けた、通称「マントラ・セッション」。
ミナスの州都ベロ・オリゾンチの代表的ホール「チアトロ・セジミナス」で行われたもので、同内容のショウは今年2010年の年末にも予定されているそう。
音声が鮮明でないのが残念だけど、壮大な演奏が展開されていたことは充分に伝わります。
09年来日時のマントラ・セッション(4月26日/鎌倉・光明寺)の動画はこちら
マントラをコンセプトとしたアルバム『サウンズ:平和のための揺らぎ』
2010.01.22
ハイチ地震募金 iTunes Storeにて受付中
紹介が遅くなりましたが、ハイチ地震の募金をiTunes Storeにて受付しています。(こちらのサイトで知りました)
1/23に行われるチャリティーイベントのライブアルバム売上が各機関へ100%寄付されるほか、
今すぐアメリカ赤十字社に募金することも可能。
iTSのアカウントを持つことが必要だが、手続きは簡単で、500円から募金額を選択できる。
ハイチにはまだ行ったことがないけれど、その素晴らしさは、やはり音楽から推し量ることができる。
20才前半の頃、小規模チェーン展開している「cafe HAITI」によく行っていた。ここでいわゆる現地のポピュラー・ミュージック「ヘイシャン」がよくかかっていて、黒くて、まろやかで、びっくりするぐらいファンキーな曲がかかることも度々あった。お店の人に伺うと、
「昔この店にハイチの音楽に詳しいスタッフがいてね、そいつが作ったカセットをずっと流してるだけだから。」
ということで、アーティスト名も何もわからずじまいだった。でもそのうち、あんまりこちらがしつこいからか、奥のほうに放置されっぱなしになっていたらしいLP数枚を譲っていただいたのだった。
この店では、コーヒー豆の仕入れついでに、LPを買い付けしていた時期があるらしい。それが確か70年代末~80年代初頭ぐらいの話で、その大多数は中村とうよう氏が買い占めていったとのこと。
そんなことがあってからというもの、ずっとハイチの音楽が気になっていて、パリやNYに行く際には注意して探すようにしている。後日そんなオススメのアルバムも紹介していければと思うけれど、そこで伝わってくるポルトープランスの風景も、この地震によって一瞬にして変わり果ててしまったに違いない…。犠牲者のご冥福をお祈りします。
2010.01.12
Best Disc 2009 【All Genre】
09年は耳を通す新譜の枚数がさらに増えて、月120~150タイトルにものぼっただろうか。
そのうちブラジルものの割合はせいぜい15%、20枚程度だから、毎月毎月100枚以上、ヒップホップからクラシック、各国のトラッドや民族音楽に至る、様々な国の面白い音楽に出会ったということになる。
このblogや当レーベルに期待されているものがあるとすれば、それはやはりブラジルものに他ならないとは思うけれども、とはいえ元々色んな音楽を経由してブラジルに行きついたリスナーがほとんどだと思うので、ブラジル以外の【オールジャンル・ベスト】も5枚だけご紹介します。
ブラジルにどっぷり一直線、という人も手にとってもらえたら嬉しいです。
#1: V.A. /DARK WAS THE NIGHT
09年はよく言われるように、いわゆる“ブルックリン勢”を軸に、カナダを含めた北米のオルタナティヴが面白かった。エイズ・チャリティの名物シリーズ最新作は久々にこの界隈のアーティストがメインで、ダーティー・プロジェクターズ(+デヴィッド・バーン)に、ファイスト2曲(それぞれGrizzly Bear, Ben Gibbardとの共演)、クロノス・クァルテット、キャット・パワー&ザ・ダーティー・デルタ・ブルーズ、スフィアン・スティーヴンス、etc, etc...といつもながら聴きどころ満載。サウンドはどれも地味で荒涼としてるけど、その反面、生きた人間のぬくもりが伝わる歌声の持ち主ばかりで、全体に一貫して流れるロードムーヴィー的なストーリー性にも大いに魅了された。
DARK WAS THE NIGHT on Myspace
#2: 坂本龍一 /OUT OF THE NOISE
正直なところ、これまであまり興味が湧くことのなかったアーティストで、お勉強的に5枚ぐらい聴いたアルバムも全くピンとこなかった。あらゆるメディアで展開される露出戦略も、あまりいいイメージを抱けなかった理由の一つという気がするのだけれど、これは掛け値なしに素晴らしい一枚。現代音楽、環境音楽、ミュージック・コンクレート、エレクトロニカ、、、といったバックボーンで語れる音楽には違いないけれど、全然そんな言葉じゃ伝わらない奥行き、音の出どころの深さが感じられる。スピーカーやヘッドフォンから、こんな根源的な音を鳴らせるのか、という驚き。
#3: MOCKY /SASKAMODIE
ファイスト、ゴンザレス、そしてこのモッキーに、近頃もっとも「フレッシュさ」を感じる。これも60'sモータウン的な希望に溢れたレコード。
MOCKY on Myspace
#4: MAXWELL /BLACK SUMMERS' NIGHT
8年ぶりのアルバム、それも、相変わらずの生音ヴィンテージ志向。で、ビルボード初登場1位。それだけセックス・シンボルということなんでしょう。ニュー・クラシック・ソウル、とかいう言葉もありましたが、この人の場合、単に「ニュ-・ソウル」としたほうが雰囲気がよく伝わる(ただし、70'sニュー・ソウルの単なるレプリカではない魅力もちゃんとある)。本質的な甘さ、ほろ苦さが、既に老舗の味わいのように生きている音楽。
The Official Maxwell Youtube Channel
#5: MELODY GARDOT /MY ONE AND ONLY THRILL
語尾が少し震える感じとか、思わず耳を「そばだてて」しまう歌声に、不覚にもやられてしまった。ティン・パン・アレイ(もちろんNYのほう)の名曲みたいなクラシカル感をあらかじめ兼ね備えた楽曲も素晴らしい。交通事故から復帰するため、セラピーのために作曲を始めた、という有名なエピソードも嫌いじゃない。
MELODY GARDOT on Myspace
2010.01.03
【Brasil Best Disc 2009】 #1: Ana Costa "Novos Alvos"
あくまで自然体、等身大の女性の心情を歌いながら、本物のサンバだけが持つポエジーをものした傑作2ndアルバム。
サンバにも色々あるけど、晴れた日に口笛吹きながら、物憂い日でもとにかく海をめざして歩いていく、これはそういうサンバだ。全体に風通しがよく、伸び伸びと心地よいけれども、陰影はくっきりと深い。何よりまず優れた楽曲が揃っていて、歌声から伝わるたたずまいが美しい、というシンガーソングライター作品に求められる魅力がしっかり備わっている上に、リオの空気、カリオカの生活感が、アルバム全体を通して鮮やかに伝わってくる。
ちなみにプロデュースはアレ・シケイラで、前掲のマリーザ・モンチ、カルロス・ヌニェス作品も手掛けているキーパーソン。音響的にも新味があって、眩いなあ。フリー・ソウル的な雰囲気の1stもオススメです。
2010.01.02
【Brasil Best Disc 2009】 #2: Daniela Mercury "Canibália"
近年のダニエラ・メルクリ作品の充実度は本当に目を見張るものがあるのだけれど、ある時期にセンセーションを起こしたシンガーの例によくあるように、日本ではデビュー時のイメージが仇となってなかなか理解されていないように思える。ダニエラにとっての“仇”とはもちろん、バイーアのダンサブルなポピュラー音楽としての「アシェー・ミュージック」で、これを狭義で捉えれば「パラパラのラテン風みたいなアレ」ということになる(批判じゃないです、念のため)。このアシェーという言葉、現地ではかなり広い意味で使われる、この国特有の宗教的な言語表現の一つで、手元の辞書を開くと【オリシャ(カンドンブレ、ウンバンダなどの神)の霊力; その力が宿る物】とある。ダニエラ・メルクリの音楽を語る上で、「アシェー」を後者の意味で使うなら、これ以上ふさわしいものはない。
歌に秘められた霊性や念の強さは、まるで70年代のエリス・レジーナ(04年に発表したアコースティック編成のライヴ・アルバム『Clássica』では、エリス直系といっても過言ではないサウンドを展開してみせた)。エリスが霊媒のごとく突き抜けた歌唱の持ち主だとすれば、ダニエラは、もっと地平に近いところから、天を真っ直ぐ見上げて祈るようなストリート感覚がある。サウンド面でも、アフロ・バイーアのエッセンスをワイルドかつグローバル・モダンに昇華した超・力作。このブログをチェックされているような方は、まず全員必聴です。
2010.01.01
【Brasil Best Disc 2009】 #3: Caetano Veloso "Zii e Zie"
09年は北米のロック・カテゴリーにいい作品が多かったように思うけれども(後述)、まさかカエターノに、3ピースのロック・バンドをバックにしたこんな傑作を作られては、若い世代は出る幕がないじゃないか。
カエターノは元々ニルヴァーナが大好きで、今作ではピクシーズにも強い影響を受けているらしく、一聴すると確かにオルタナティヴ・ロックの手触りなんだけれど、同時に「サンバを超えたサンバ・アルバム」というコンセプトを元にすることで、ピクシーズがサンバをやったような本作が産まれた(いや本当に)。素をさらけ出したカエターノも魅力的だけれど、ギターのペドロ・サーを中心としたこのバンドがなんともスリリングで、ロックにおける3ピース・サウンドの歴史を塗り替える斬新さ。
メンバーは同じだが、よりロックのイディオムに拠っていた前作『Cê』がイマイチだったという人も(私がそうです)、ぜひ一聴することをオススメします。
カエターノ・ヴェローゾ公式hp/zii e zie特設ページ
※こちらで全曲聴けます。(原稿投稿時)
2010.01.01
【Brasil Best Disc 2009】 #4: Egberto Gismonti "Saudações"
あけましておめでとうございます。Happy New Year & Feliz Ano Novo!
今年もみなさまが良き音楽生活を送られますよう。
本当は旧年中に1位までupするつもりだったのだけど、やっぱりだめだったなぁ、、、
まあ、2010年もゆっくりやっていきますので、よろしくお願いします!
1位にするかどうか最後まで迷った、でも、2位とか3位っていうのは全然似合わない音楽。
ジスモンチが一般にどうイメージされているのか今ひとつ不明なのだが、ギター好きには「現代屈指のギターの巨匠」だろうし、ジャズ・ファンなら「ECMの鬼才」っていう感じだろうか。表現的にも技巧的にも飛びぬけてオリジナルな音楽なので、どう捉えればいいかわからない、というのが大方の意見かもしれない。
持論を述べれば、「現代コンテンポラリー・シーン最高の作曲家」であり、同時に、アルゼンチンでいうところのアストル・ピアソラに匹敵する存在だと、信じて疑わない。
ピアソラは、タンゴ・ファンからの評価が賛否両論激しく分かれるが、そうしたことを含めて、とにもかくにもタンゴを背負った。一方のジスモンチは、ブラジル、とりわけアマゾンの心象風景を負うている。本人がどこまでそんなことを意識しているか不明だが、そう聴こえてしょうがないのだ。クラシックから民族音楽までを横断し、アマゾンから多くのインスピレーションを受けている存在といえば、20世紀音楽の巨匠・ヴィラ=ロボスがすぐ思い浮かぶが、ヴィラ=ロボスの「アマゾン」から感じ取れる雄大さ、野趣溢れるメロディの美しさ・力強さ、といった要素を引き継ぐだけでなく、ある種の切迫した響き、失われつつあるものへの畏敬の念といったものが感じ取れるのが、ジスモンチの音楽の特徴という気がしている。現代資本主義社会への警告、なんてことを念頭に作曲しているわけではないとしても、どこかでそういった時代の空気を反映しているに違いない。
前置きが長くなったが、これはジスモンチ久々の新録作品。キューバの女性のみによる弦楽オーケストラ「Camerata Romeu」が演奏したディスク1と、実の息子アレシャンドリ・ジスモンチとのギター・デュオによるディスク2からなる2枚組。前者は『セルタンへの道 ― 混血礼賛』というサブタイトルがついているが、彼ならではの旋律と色彩感が表現された、いわば「観念としてのジスモンチ」作品。一方のギター・デュオ・サイドは、当然ながら本人の演奏を軸にしていて、より肉体的で、ドライヴ感に溢れる作品集。「Lundú」「Dança dos Escravos」といった代表曲の再演もある。ギターのヴィルトゥオーゾというイメージが強いジスモンチだけど、本人はピアニスト志向のほうがむしろ強いらしく、そのピアノが聴けないという点で最初に手に取るべき一枚かどうかは難しい点だが、傑作であることは間違いない。
2009.12.29
【Brasil Best Disc 2009】 #5: Arlindo Cruz "MTV Ao Vivo"
一世紀近いサンバの歴史のなかで、おそらく最も多くのアーティストに歌われてきたコンポーザー、アルリンド・クルス。古くはベッチ・カルヴァーリョ、比較的最近ではマリア・ヒタの目下のところの最新アルバム『サンバ・メウ』で6曲、それも新曲ばかりを取り上げられたこともあり、何度目かのピークを迎えています。これは新旧のヒット曲を自演した2枚別売りのライブ・アルバム/1枚組DVDとして発売されたもので、もう、ひたすら美メロのオンパレード。その巨漢から発せられるかん高い声で、人生の機微、泣き笑いが入り混じったメロディを歌われると、ついつい大声で歌いたくなってしまいます。男泣きするメロディ、っていうものがあるとすればこんな感じ。
2009.12.29
【Brasil Best Disc 2009】 #6: Gilberto Gil "Banda Dois"
声とギター、ふたたび。
年末ぎりぎりに間に合ったジルの新譜は、09年9月のショウを収録したCD/DVDで、自身のギターとヴォーカルに、息子ベン・ジル(ギター、パンデイロ、タンボリン)の二人だけを基本としたごくシンプルな編成。(マリア・ヒタがゲストで、亡き母エリスにジルが提供した名曲「Amor Até o Fim」を歌っているけれど、この作品においてはそれも余興ということで。)
さらに、レパートリーも2曲を除いて全て自作曲、とくれば、ありがたくもこの日本で最もヒットしたジルのアルバム『声とギター ジル・ルミノーゾ』のことが誰でも浮かぶと思うが、まさにその続編と捉えて差し支えない。しかも重複曲は1曲だけ!
サンバ、ボサノヴァ、アフロ・バイーア、レゲエ、フォーク、ブルース…といったパフォーマーとしてのサウンド変遷と、コンポーザーとしての魅力が「声とギター」に集約された、ジルにしか為し得ない弾き語り(+1)表現、心ゆくまで味わってください。
以前もこのブログで書いたけれど、時代ごとにサウンドの振れ幅が広いアーティストの宿命ゆえ、何かと誤解されることの多い代表的アーティストというイメージがある。だからこそ、最初にこうしたシンプルな編成で本質を掴んでおくと、その後の印象が全く変わってくるのでは。マッチョなイメージを持っている人ほど、新たな発見があるのではないでしょうか。
公式hpで「全曲通しで」試聴できるので、じっくり聴いてみてください。
2009.12.28
【Brasil Best Disc 2009】 #7: Marisa Monte "Infinito Ao Meu Redor"
この辺りから、どれが1位でもおかしくない傑作揃い。ちなみに順位は、シンプルにおすすめ順です(開かれた音楽ファンのための)。
マリーザ・モンチの最新ライブDVD+CDというフォーマットのこのアルバムは、2006~07年にわたって行われたツアーを収めたもので、来日公演時にも披露されたレパートリーが収録されている。2006年に発表された2枚のアルバム『私の中の無限』(通称:ポップ盤)、『私のまわりの宇宙』(通称:サンバ盤)のレパートリーが中心で、特に『私の中の無限』は、マイ・ブラディ・ヴァレンタイン『Loveless』以来の革命的ポップ・レコードだと思っている。発売当時、他にそんなことを言う人は一人もいなかったので、自分だけの感想かと思っていたのだけれど、2007年の来日時にintoxicate誌にそのことを書いたら思わぬ反響をいただいた(下記に転載するので、ご興味のある方はご一読ください)。この原稿執筆から4年経とうとしている今も、この『私の中の無限』、さらに2007年の来日公演の風評は全く風化していない。
と、前作のことばかりになってしまったが、名曲「Alta Noite」の素晴らしい再演もあり、ファンは必ず手にして欲しいライブ作品です。マリーザの最初の一枚がこの作品でももちろんOK!
○
"It set a new standard for pop. It's the vaguest music ever to have been a hit”―ブライアン・イーノが、マイ・ブラディ・ヴァレンタインの名曲「Soon」について語った有名なセリフである。マリーザ・モンチ6年ぶりの新作『私の中の無限』、通称[ポップ盤]を聴いてすぐに思い起こしたのがこの言葉であり、「Soon」を収録したMBVのアルバム『Loveless』を初めて聴いたときの、得も言われぬ感覚だった。
むろん、この2作に直接的な関係があると言いたいわけではない。だが、なにか新種のポップ・ミュージックが生まれ、シーンにインパクトを与えた例として、ひたすらに審美的な世界観、抽象的な(イーノは“vague”と表現したけれど)サウンドでこれを成し遂げた作品はそう多くない。まさかそのような体験を、ほかならぬマリーザのアルバムですることになると誰が予想しただろう…。けれど、もちろん、布石はちゃんとあった。
88年のデビュー以来、発売したアルバムは全て50万枚以上のヒットを生み、ブラジル屈指の人気を誇るマリーザ・モンチ。メロディの故か、または声の力か、不思議に判別しがたく存在する音律の美しさが何よりの魅力だが、これと溶け合い、絡み合うような本作のアレンジが凄い。ギター、ベース等のレギュラー・セットに加え、自身のウクレレ、スティール・ギター、タブラといった独創的な編成に、フィリップ・グラス、ジョアン・ドナート、デオダートという3人のマエストロが管弦の指揮を揮ったサウンドは、ヒット・チャートのトップを飾る音楽としてはあまりに幻想的で、浮遊感に溢れたものだ。だが思えば、マリア・カラスのようなオペラ・シンガーを目指していた時代もあったと聞くし、3作目の『ROSE AND CHACOAL』以降は、ストリングスや管のクレジットも増え、シンフォニックな音響を重視する傾向にあった。前作までのプロデュースを務めたアート・リンゼイをはじめ、坂本龍一、ジョン・ゾーン、マーク・リボーといったNY前衛シーンの面々とも常に交流があったし、今振り返ると、ほとんどどんな高度な音楽を具現化してもおかしくないではないか!
一方、同時発売された『私のまわりの宇宙』では[サンバ盤]という通称どおり、一世紀近い歴史を持つサンバにフォーカスした内容。メロディや詩世界にも独特の美学を持つこの音楽を、通常サンバには使われないハープやアナログ・シンセ類、テルミンやヒューマン・ビートボックスまでを導入、斬新だが軽やかに再生してみせた。
さてそんなマリーザの15年ぶりの来日公演だが、ブラジル・ツアーと同メンバーによる10人編成で、管弦カルテットを含む万全の布陣が決定。このメンバーでは上記の2作だけでなく、トリバスタスや初期の作品も演奏しているとのこと。レコード発売時以外はライブをあまり行わず、本国ではチケット入手の難しさで知られる彼女だけに、これを逃すと、次はいつになることやら…?
2009.12.26
【Brasil Best Disc 2009】 #8: V.A. "O Baile Do Simonal"
1960-70年代に活躍した“サンバ・ソウル・エンターテイナー”、ウィルソン・シモナル。レアグルーヴ以降、この日本でも再評価熱が高まったシンガーの一人でもある。その実の息子たちで、それぞれソロ・アーティストとして活躍するウィルソン・シモニーニャとマックス・ヂ・カストロが中心となり、豪華ゲストを招いて亡き父に捧げたトリビュート・ライヴ・アルバムがこれ。そういえばこのウィルソン・シモニーニャとマックス・ヂ・カストロも、00年代前半頃には渋谷系アーティストからレコメンドされることも度々あった。
日本やイギリスと同じく、いやひょっとするとそれ以上に、サンパウロやリオの人々は70年代のアメリカン・ソウル・ミュージックが好きなようで、現在進行形のポップ・ミュージックの中にもそのエッセンスを感じる機会は多い。歌が好きで、パーティー好きな国民性を考えれば納得のいく話ではある。ピアノを中心としたスウィングするバンド、ホーン・セクションをバックに、気分はSamba SOUL TRAIN!サンバを消化したリズム・アレンジに、優れたソウル・ミュージックだけが持つ、圧倒的にポジティヴなヴァイブが流れてます。この、60年代のモータウンのレコードにあったような希望に溢れた音、これがこのアルバムの一番の魅力かも知れない。パーティーにも重宝しますよ!
01. País Tropical / Seu Jorge
02. Carango / Samuel Rosa
03. Nem Vem que Não Tem / Marcelo D2
04. Mamãe Passou Açúcar em Mim - Mart´Nália
05. Aqui é o País do Futebol / Wilson Simoninha
06. Meia-Volta - Rogério Flausino
07. A Tonga da Mironga do Kabuletê - Fernanda Abreu
08. Meu Limão, Meu Limoeiro - Max de Castro
09. Está Chegando a Hora - Diogo Nogueira
10. Na Galha do Cajueiro - Péricles & Thiaguinho
11. Vesti Azul - Roberto Frejat
12. Que Maravilha - Maria Rita
13. Mustang Cor de Sangue - os Paralamas do Sucesso
14. Balanço Zona Sul - Sandra de Sá
15. Terezinha - Orquestra Imperial
16. Lobo Bobo - Ed Motta
17. Remelexo - Caetano Veloso
18. Sá Marina - Alexandre Pires
19. Zazueira - Lulu Santos
2009.12.25
【Brasil Best Disc 2009】 #9: V.A. "Nego"
アメリカン・スタンダード、それもジャズのレパートリーとして広く知られるレパートリーを中心に、MPBオールスターズが「ポルトガル語で」カヴァーした作品。
そんな本作のコンセプトを耳にした時点で早くも興味を失ってしまう向きには、こう説明するのがいいかもしれない――これは、この半世紀に渡って大量に生み出されてきた「ボサノヴァ曲の安易な英語カヴァー」に対する意趣返し、反撃なのだ、と。
曲目と参加アーティストは下記を見ていただくとして、何より、これは実質的にジャキス・モレレンバウンのアルバムなんである。プロデュース(Carlos Rennó、Moogie Canazioと共同)、全曲のアレンジを担当しているほか、チェロも演奏している。チェロに関しては、一人オーケストラ状態のダビングで臨んだ曲もいくつかある。
ジャキスといえば言わずもがな、カエターノ・ヴェローゾの音楽監督として、また晩年のアントニオ・カルロス・ジョビンの音楽的パートナーとしての仕事が何といっても有名だが、それら作品群のファンならまず外さない「流麗で」「高貴な」絶品の内容だ。スタンダード集としてリラックスして聴ける作品には違いないけれども、時おりジャキスの演奏に一抹の狂気を感じる瞬間があって、本気度が伝わってくる。
ガル・コスタの歌う“My Romance”、エラズモ・カルロスの“Summertime”あたりだと原曲にすぐ気付くけれども、多くの曲はブラジルの楽曲に聴こえてくるから面白い。
名演揃いだけど、セウ・ジョルジの“Strange Fruit”は鬼才としかいいようのない最高の仕上がり。モレーノ・ヴェローゾの“How Deep Is The Ocean”も美しい。
01. MEU ROMANCE
(MY ROMANCE)
Gal Costa
02. INQUIETA, TONTA E ENCANTADA
(BEWITCHED, BOTHERED AND BEWILDERED)
Maria Rita
03. TÃO FUNDO É O MAR
(HOW DEEP IS THE OCEAN)
Moreno Veloso
04. VERÃO
(SUMMERTIME)
Erasmo Carlos
05. ESTAVA ESCRITO NAS ESTRELAS
(IT WAS WRITTEN IN THE STARS)
Emílio Santiago
06. NEGO
(LOVER)
Paula Morelenbaum
07. SÁBIO RIO
(OL' MAN RIVER)
João Bosco
08. FRUTA ESTRANHA
(STRANGE FRUIT)
Seu Jorge
09. TENHO UM XODÓ POR TI
(I'VE GOT A CRUSH ON YOU)
Elba Ramalho / Dominguinhos / João Donato
10. QUERIA ESTAR AMANDO ALGUÉM
(I WISH I WERE IN LOVE AGAIN)
Ná Ozzetti / Wilson Simoninha
11. O HOMEM QUE PARTIU
(THE MAN THAT GOT AWAY)
Luciana Souza
12. MAIS ALÉM DO ARCO-ÍRIS
(OVER THE RAINBOW)
Zélia Duncan
13. NATAL LINDO
(WHITE CHRISTMAS)
Olivia Hime
14. MEU ROMANCE
(MY ROMANCE)
Gal Costa e Carlinhos Brown
Jacques Morelenbaum on MySpace
★Moreno Veloso "TÃO FUNDO É O MAR (HOW DEEP IS THE OCEAN)" のみ聴けます(投稿時)。
2009.12.23
【Brasil Best Disc 2009】 #10: Carlos Núñez "Alborada do Brasil"
今年のブラジルはビッグネームの充実作が多かったこともあり、いつにも増して「豊作」との声がよく聞かれた。来日公演もそこそこあったし、ファンにとって記憶に残る一年だったのでは。
でも、現場で聞くそんな声と相反するように、日本盤のCDリリースは激減。ということはこうした音楽が宣伝される機会がかなり減っていることを意味するわけで、これについてはレーベルとしても音楽ライターとしても、もっと頑張ります、というひと言に尽きますが…。会社としても、いち音楽ファンとしても、自分の好きなものがこの世から失われてしまうことのないように尽力していければと思っております。(固っ!)
そんなことを書いたのも、ミュージック・マガジン2010年1月号のベスト・アルバム企画で、「ブラジルの新録にあまり面白いものがなかった」なんて未だに書かれているのを目にしたからでした。当誌は毎年のように、この年末企画で同じ趣旨のことを発表し続けているのだけれど、仮にいちライターの(今号では原田尊志さん)嗜好でそう思ったとしても、音楽ファンの間での高い評判が公に伝わっていれば、編集者だってこうした記事の掲載については考慮せざるを得ないだろう。(それにしても、「ラテン」というカテゴリーを独立させたうえでのこの発言では、雑誌としての編集意図に?が浮かばないだろうか。)
ようするに、認識不足の問題なのだ。その魅力を知る人たちが、こうした風評を吹き飛ばしていくしかない。
ということで、前置きが長くなりましたが、2009年のベスト・ディスクです。
みなさまの音楽生活に活力をもたらす、いずれもエモーショナルな作品揃いです!
○
Carlos Núñez "Alborada do Brasil"
カルロス・ヌニェスはガリシアのパイプ奏者で、ケルト音楽界のスター・プレイヤーの一人。どこがブラジルやねん!とのツッコミが聞こえてくるけれど、これが近年稀に見る超大作で、あえてこちらで紹介したい。
率直に言ってこの人の作品は今までどれもピンとこなかったのだが、プロデュースにアレ・シケイラやマリオ・カルダートJr.を、さらにゲスト・プレイヤーにアドリアーナ・カルカニョット、カルリーニョス・ブラウン、レニーニ、フェルナンダ・タカイ、カシン、ジャキス・モレレンバウン、ヤマンドゥ・コスタ、ドミンギーニョス、etc...を迎えたブラジル録音と聞けば、どうしたって聴かないわけにはいかない。
カルロスはこのアルバムで、ガイタ(ここではハーモニカではなく、ガリシアのバグパイプのほう)だけでなく、フルートやホイッスル、オカリナなど様々な木管を使い分けているのだけれど、それらをあくまでガリシアン・ケルティック節で吹ききっているのがこのアルバムの面白いところ。本人のオリジナルと共に、カルトーラの“Alvorada”、ミルトン・ナシメントの“Ponta de Areia”のように、ブラジルのリオやミナスの風土が連想される曲をカヴァーしているのだが、既知の感覚と未知の色彩感が交差する、何とも摩訶不思議な印象を残すのであった。
ラティーナ11月号のインタビュー記事によると、ガリシアとブラジルは、言語的にも人種的にも類似点が多く、特にバイーアには多くのガリシア移民が住むという。彼の説によれば、ブラジル音楽のメロディにはバグパイプの影響が見られるという。また彼の曾祖父は、サンバの源流のひとつとも言われる舞曲のスタイル「マシーシ」を作り出した人物だった、とも。摩訶不思議、と言ってみたけれど、19世紀のブラジル音楽には、意外とこんな雰囲気があったのかもしれない、そんなことを思わせたりもする。プロデューサーのアレ・シケイラとマリオ・カルダートといえば、マリーザ・モンチの最近作を担当した制作陣で、極めて現代的なポップス作品に仕上がっていることはもちろんなのだが、同時に19世紀の、希望に満ち溢れた、輝かしい響きまでをもパッケージしたかのような仕事ぶりにも、魔力を感じる。
色んな音楽を聴けば聴くほど、やっぱりブラジル音楽は面白い。
2009.10.15
『ジョビン、ヴィニシウスを歌う』 intoxicate誌に紹介されました。
タワーレコード発行の音楽誌“intoxicate”10/10発行号にて、
『ジョビン、ヴィニシウスを歌う』が記事として取り上げられています。
執筆者はbar bossaの林伸次さん。
先日このblogでも少し書いたけれど、ピアニストの中島ノブユキさんの名盤『エテパルマ』の構想は、このジョビンのアルバムから生まれたのだそう。林さんらしく、バーのお客さんとマスターの会話を通して、この『ジョビン、ヴィニシウスを歌う』の魅力について語られる楽しい文章です。
他にも色んなメディアがこのアルバムを紹介してくれることになっているけれど、なかでもこの記事はダントツで面白かったです。エピソードを交えた柔らかい文章で、色んな視点を発見できる文章なので、ぜひご一読を。誌面としても日本の音楽誌では1、2を争う充実度ではないでしょうか。
2009.08.24
Affonsinho & Joyce
さる8月16日、アフォンシーニョとジョイスのジョイント・コンサートが、ミナス・ジェライス州都ベロ・オリゾンチのParque Municipalで行われた。ここはベロ・オリゾンチ市街のいわば「セントラル・パーク」。敷地内にはちょっとした遊園地なんかもある。週末には公園脇に蚤の市がたつので、ベロ・オリゾンチ観光の際は足を伸ばしてみては。
ちなみに今アフォンシーニョは新作のレコーディング真っ最中で、前作『ベレー』の延長線上にあるポップな内容、とは本人の談。前作はブラジル以外で活躍されている識者の方々からも好評で、シンガーソングライターとしての力量の高さが証明された傑作だと思っている。夏の終わり~秋にかけて聴いてもまたいい感じです。
2009.08.17
Cesar Camargo Mariano × Romero Lubambo × TM
NY在住のとある日本人女性シンガーのプロデュース依頼を受け、今年2度目のNY出張中。
マンハッタン、チェルシーのちょっと北側にあるクリントン・スタジオに籠もって朝から晩までレコーディングしているのだが、このメンバーが面白い。
まず彼女を発掘した張本人で、演奏はもちろん、アレンジ・選曲を含むミュージック・ディレクションを担当しているギタリスト、ホメロ・ルバンボ。最近ではダイアナ・クラールなど、ジャズ・シーンでも活躍するブラジル有数のテクニシャンだが、個人的にはホメロといえば、マリーザ・モンチ『アモール、アイ・ラブ・ユー』など、シンガーの魅力を引き出す歌伴アプローチが最高のプレイヤーだと思っていて、その資質をいかんなく発揮してくれた。
他にもジョイスの近作のレコーディングで知られるピアニストのエリオ・アルヴェス、Tzadikからの新譜も面白かった鬼才パーカッショニスト、シロ・バチスタに、1972年以降のエリス・レジーナのほぼ全作品のアレンジを手掛けたセーザル・カマルゴ・マリアーノの参加と、豪華なメンバーが勢揃い。
写真はセーザル、ホメロ、主役シンガーとのトリオのもの。「ペギー・リーのような美しい声だ」と感激したセーザルが、アメリカン・スタンダードをやりたいと急遽提案し、譜面はもちろん歌詞カードもないなかリハーサルしている場面。今回レコーディングしたどのトラックにも言えることだが、その後2テイクでOKを出してしまったこのシンガーの詳細については、また後日報告します。
2009.01.02
【Brasil Best Disc 2008】 選外: V.A. "Samba-Nova"
選外 V.A. "Samba-Nova" (NRT)
自分で選曲してリリースしたものなので、順位はちょっと付けられないかと。
単純にいいメロディ・表現力豊かなサウンドの極致という感じなので、どんな用途でも楽しんでいただけたらこの上ない喜びなのですが、せっかくですからここから色んな方面に手を伸ばしていただけたらなお最高です。
「アーバン・ポピュラー・ミュージック」であるサンバが、現在いかに多彩に発展し、文化的な洗練を経ているか、おわかりいただけると思います。スタジオ・ボイスやミュージック・マガジンの特集をはじめ、本当に色んな雑誌で取り上げられたのも、新鮮さを感じてもらえたからなのでは。
ひたすらメロウで、フレッシュな音楽です。
2009.01.02
【Brasil Best Disc 2008】 #1: アドリアーナ・カルカニョット "マレー"
第1位 アドリアーナ・カルカニョット "マレー" (BMGジャパン)
月刊ラティーナ08年8月号で書かせてもらったインタビュー記事冒頭で、宮子和眞さんによる「現代におけるマリーザ・モンチとアドリアーナ・カルカニョットは、70年代のキャロル・キングとジョニ・ミッチェルに相当する才能だ」という趣旨の文章を引用させてもらったが、成熟した音楽ファンに対して、この人の音楽を原体験できる幸福をアピールするうえで、有効なフレーズだと改めて思う。
もちろんアドリアーナの音楽は、カエターノやドリヴァル・カイーミらブラジルのコンポーザーからの影響を受けているし、またその系譜に位置するシンガー・ソングライターであることは間違いない。けれども彼女の場合はそうしたサウンド面での影響云々よりも、表現されているストーリー性や、その詩的な世界観が最大の魅力だろう。
ある種の絵画や文学がそうであるように、人はそこに描かれた線や色、言葉のフレーズをただ楽しむだけでなく、全体を覆う気配や感情、背後にある物語を体験することができる。この音には風景や色彩があり、ときおり怖くなるほどの孤独の感情と、何にも縛られることのない自由な感覚、いくつもの眩い生の瞬間がある。
ドメニコ・モレーノ・カシンの「+2」トリオとデー・パルメイラによる、ごく音数を絞った、それでいて独創的なサウンドも、中毒性を一層高めることに貢献している。
2008.12.31
【Brasil Best Disc 2008】 #2: ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート "ジョアンに花束を"
第2位 ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート "ジョアンに花束を" (NRT)
彼らの作品をリリースするのはこれで5枚目になるから、このブログを見てくださっている方には、お馴染みのデュオといっていいかもしれない。メロディメイカーとしての確かな力量とその端正な歌声で、世界中にあまた存在するシンガー・ソングライターの中でも最高の水準に位置するものと思っている。聴く人を選ばぬ親しみやすい音楽だけれど、精神的に澄み切った、邪念のない高みに連れて行ってくれるこんな音楽は、ちょっと他に見当たらない。
さて、このアルバムで注目されることはと言えば、マリア・ヒタのサウンドの代名詞でもある二人のミュージシャン――チアゴ・コスタ(piano)、シルヴィーニョ・マズッカ(acoustic bass)が全面参加していること。彼らの参加で、これまでにないドライブ感や色彩感がプラスされている。そうしたサウンド面での刺激と、歌声の美しさで、音楽における文学的・詩的表現をさらに深化させた傑作だと思っている。
2008.12.31
【Brasil Best Disc 2008】 #3: Roberto Mendes "Cidade e Rio"
第3位 Roberto Mendes “Cidade e Rio” (Biscoito Fino)
ホベルト・メンデスは北東部バイーア州に位置するサント・アマーロ出身の男性シンガー/作曲家。同郷のマリア・ベターニアがよく取り上げることで知られている人だ。バイーア特有「サンバ・ヂ・ホーダ」の王道を往くスタイルで、多くの曲はA-A-B-A*といった構成に朴訥としたヴォーカルが乗るシンプルな音楽だけれど、「バイーアらしい」としか言いようのない風景や匂い、時間感覚を喚起させてくれる。南国のダイナミックな風土にありながら、なお繊細に育まれた感性が、こんな風に飾り気のない表現に結実したときの眩しさといったらない。マイナー・キーを使用せず、オープン・チューニングで演奏されているとおぼしき彼のギターも味わい深く、ハワイのスラック・キー・ギターにも通じる心地よさ。土臭さを損なわず、その実洗練されたアンサンブルも文句なし。カエターノ・ファンも必聴です。
2008.12.30
【Brasil Best Disc 2008】 #4: ジルベルト・ジル "バンダ・ラルガ・コルデル"
第4位 ジルベルト・ジル“バンダ・ラルガ・コルデル” (ワーナーミュージック)
「えっ、カエターノよりも?」
周囲のブラジル音楽リスナーに対して、ジルが自分の一番好きなアーティストであることを告げるとき、かなりの確率で戻ってくる反応がこれだ。そりゃー、両方好きに決まってるんだけどさ。マッチョな音楽性というイメージ、あーあのブラジル人なのにレゲエな人でしょ、という一面的な理解、80年代にLA録音でフュージョンとかディスコティークなサウンドを多く発表してきたこととか、ことどとくマイナスに働いてきたような印象もある。
まあ、ここでそのイメージ全てを否定しようとは思わないけれども、ジルがブラジル音楽史上、最も思索的、詩的な名曲を生み出してきたポピュラー作曲家であり、同時に身体的に優れたパフォーマーであるということは、重ねて言っておきたい。問題は、その多面的な魅力をバランスよく楽しめるアルバムが、そう多くないことにある。5枚買っても10枚買っても、買う作品や順番によっては、どんなアーティストなのか、ますます掴めない、ということにもなりかねない。
この新作のいいところは、ジルの今までのサウンド遍歴がバラエティ豊かに収まりつつ、口ずさみたくなるようなメロディにあふれ、しかもフレッシュな躍動感に満ち満ちているところにある。レゲエとフォホーが、シンプルなサンバやアフォシェーのリズムとテクノロジーが、ごく自然に溶け込んでいるこんな音楽はこの人の独壇場だが、気がつけばずいぶんと力が抜けて、ひたすら音楽と人生を楽しんでいる境地にあるようだ。
あえて言えば、個人的にはジルが歌う静かめの曲が大好きなので、弾き語りのパートなどあればなお良かった。そういう向きにはこのアルバムをオススメします。「滋味深さ」と「しなやかな黒さ」の共存した、究極の一枚です。
2008.12.29
【Brasil Best Disc 2008】 #5: Pedro Moraes "Claroescuro"
第5位 Pedro Moraes “Claroescuro” (independente)
「新世代サンバ」がどうのこうのと、誰よりも騒ぎ立てておいて何だけど、日本のメディアでSamba-Nova周辺露出が集中した今年前半は、現地シーンにあまり目立った動きがなかったなあ、というのが正直な感想。
リリースの谷間かな、と思っていたら、今年も秋以降になってから、マルチナーリアやスルル・ナ・ホーダの充実した新作などがリリースされて、改めてこのシーンの層の厚さを見せつけられた。
なかでも、このペドロ・モラエスという、ブラジル人男性には非常にポピュラーな姓と名を持つシンガー・ソングライターの8曲入りミニアルバム“Claroescuro”の個性は、ちょっとあなどれない。
経歴等はいまひとつ不明だけれど、現地のマスコミ記事など見ると、ここ数年リオの一大ライブ・スポットとして発展をとげる「ラパ地区」出身のニュー・カマー、ということのようだ。
完成度という点では荒削りだけれど、「私小説サンバ」と呼びたくなるストーリー性の豊かさ、アレンジの鬼才ぶりは、貴重な個性の持ち主だ。サンバの名曲/オリジナリティ溢れる佳曲を生み出していた70年代中期~後期のシコ・ブアルキあたりに近いフィーリングもある。
2008.04.13
グルーポ・コルポ来日公演
Photos: José Luiz Pederneiras

すでに各方面で話題のダンス・カンパニー「グルーポ・コルポ」来日公演。上の写真は今回の演目から「Parabelo」のもので、音楽はトン・ゼーとジョゼ・ミゲル・ヴィズニッキが手がけています。



そして番組でもオンエアした、カエターノ・ヴェローゾとジョゼ・ミゲル・ヴィズニッキが音楽を手がける演目「Onqotô」。写真だけでも伝わるこのテンション!
公演情報をこちらにも再度告知しておきます。
★GRUPO CORPO グルーポ・コルポ来日公演★
■公演日程:2008年4月24日[木]19:00開演 / 4月25日[金]19:00開演
■会場:Bunkamura オーチャードホール
■上演プログラム:『Parabelo』『Onqotô』
(※音楽は両プログラムともテープを使用します。)
■料金:S席6,500円 A席5,500円(全席指定・税込) ※未就学児童の入場不可
■お問い合わせ:Bunkamura 03-3477-3244(10:00-19:00)
2008.04.03
新 "blog Samba-Nova" こちらに移転しました。
2008年4月より、blog Samba-Novaはこちらに移転しました!
「音楽を紹介する」ということが好きで―レーベル運営(4年)、音楽ライター(5年)、DJ(15年)というチャンネルを通してこれまでやってきたけれど、他にもまだまだ選択肢がある気がしています。
個人として共感したものや出来事について、よりダイレクトに、できるかぎりダイナミズムを失わないかたちで紹介するいくつかの方法について、今年度はあらたにチャレンジしようと思っています。
というわけで本年度からは色々とこまめにアップしていきますので、よろしくお願いします。
※過去ログは右のBOOKMARKからどうぞ。